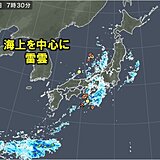<気象予報士が振り返る「平成の災害」⑨>地震・火山災害編(平成11年-20年)PR
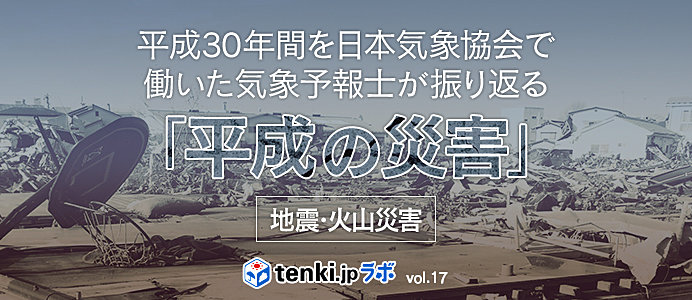
平成11年~平成20年に発生した地震・火山災害のうち3つの地震・火山災害について解説します。
【平成12年3月】平成12年有珠山噴火

火山灰、噴石、泥流による被害のようす
これを受けて、周辺の市町村では、同日に避難勧告および避難指示が出され、噴火前に約16000人が避難しました。
その後、同月31日午後1時7分に23年ぶりの噴火が発生、噴煙は約3000m以上に達し、さらに4月1日には次々と噴火が発生しました。
インフラなどは、火山噴火により大きな被害を受けましたが、これだけの規模の噴火であったにも関わらず、行政・火山専門家・住民が連携し、噴火前に住民らが避難を行ったことで一人の犠牲者も出ませんでした。
【平成12年9月】平成12年三宅島噴火

平成12年8月18日の噴火のようす(出典:気象庁ホームページ)
7~9月にかけて山頂噴火が繰り返され、8月18日の噴火では噴煙の高さが14000mにも達し、同月29日の噴火の際には低温の火砕流が発生しました。
同月31日に火山噴火予知連絡会が「今後、高温の火砕流の可能性もある」と見解を発表したことを受け、9月1日に全島避難が決定。4000人あまりの島民が島外での避難生活を余儀なくされました。
その後、二酸化硫黄を主とする大量の火山ガスの放出などにより、噴火による直接の犠牲はなかったものの、島外避難は約4年半にわたり、平成17年2月1日にようやく避難指示が解除されました。
【平成16年10月】平成16年新潟県中越地震

地震による被害のようす(出典:新潟地方気象台ホームページ)
さらに同日午後6時11分、34分頃には、最大震度6強の強い地震が立て続けに発生。
斜面崩壊や地すべりが発生し、河川がせきとめられて人家が水没するなど、新潟県中越地方を中心に大きな被害を受けました。
また、JR上越新幹線が乗客を乗せて走行中に脱線する事故も発生し、交通網をはじめライフラインにも多くの被害が生じました。
相次ぐ余震への不安から、車中泊を続けてエコノミークラス症候群を発症する被災者や、被災後のストレスや疲労により高齢者が亡くなるケースも多く、避難生活における課題を残した地震災害となりました。