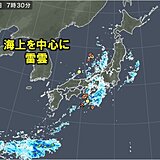<気象予報士が振り返る「平成の災害」⑩>地震・火山災害編(平成21年-31年)PR

このうち平成21年~平成31年に発生した4つの地震・火山災害について解説します。
【平成23年3月】平成23年東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)

津波によるの被害のようす(出典:東北地方整備局)
この地震(津波および余震含む)による被害は、死者19689人、行方不明者2563人にのぼり(平成31年3月現在)、戦後最大の自然災害となりました。
また、この地震と津波により、原子力発電所事故も発生しました。
この地震による甚大な津波被害を受け、気象庁は、巨大地震による津波に対して適切かつ簡潔な表現で警報を発表するよう津波警報・注意報を見直し、平成25年3月7日から新しい運用を開始しました。
【平成26年9月】平成26年御嶽山噴火

緊急消防援助隊の活動のようす(出典:消防庁ホームページ)
紅葉シーズンの秋晴れとなったこの日、山頂付近には多くの人がいたため、死者・行方不明者が63名にのぼる、戦後最大の火山災害となりました。
当時、火山性地震が増加していた御嶽山の噴火警戒レベルは「レベル1(平常)」で、危険性が登山者に十分に伝わっていなかったことが問題視されました。
そのため、「平常」という表現は誤解を招くとして、平成27年5月から、「活火山であることに留意」に変更されました。
さらに気象庁は、平成27年8月から、いち早く噴火の発生をお知らせするための「噴火速報」の運用を開始しました。
また、火山の観測態勢を強化するため、全国48の火山に監視カメラや高性能な測器を設置するなどの対応を行いました。
【平成28年4月】平成28年熊本地震

益城町の被害のようす(写真提供:国土交通省 九州地方整備局)
いずれも最大震度7を観測し、熊本県を中心に九州地方で強い揺れを観測しました。
熊本県や大分県を中心に家屋倒壊や土砂災害が相次ぎ、多くの人的被害や住家・ライフラインへの被害が生じました。
また、強い揺れが継続して発生したため、車中泊で避難生活を送る被災者が相次ぎました。
一連の地震活動で2 度も震度 7 が観測されたのは、日本の観測史上初めてのことでした。
この地震をきっかけに、大地震後の地震活動の見通しについての呼びかけが見直されました。
その中で気象庁は、さらに規模の大きな地震への注意を怠ることのないよう、大地震後の防災上の呼びかけにおいては、「余震」という言葉を控え「地震」を使用することにしました。
【平成30年9月】平成30年北海道胆振東部地震

地盤沈下で道路や住宅が傾いているようす
厚真町で震度7を観測するなど、北海道内を中心に強い揺れを観測しました。
厚真町やむかわ町などでは広範囲で土砂崩れが発生し、住宅などが土砂に巻き込まれました。
さらに札幌市清田区では液状化で地盤沈下が発生し、道路の陥没や住宅への被害が多数発生しました。
また、地震発生直後には道内全域でブラックアウト(エリア全域での大規模な停電)が起こり、災害発生後の大規模停電時への対応について大きな課題を残す地震災害となりました。