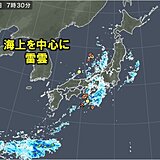<気象予報士が振り返る「平成の災害」④>インタビュー【谷口聡一】PR
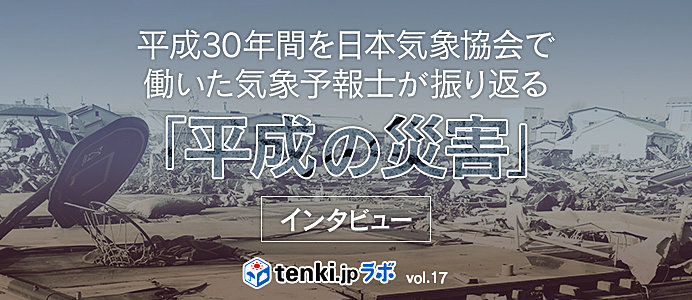

Q1 平成の気象災害の中で特に印象深かった災害は何ですか?
平成5年は冷夏によって米不足となり、海外からの米が食卓に並ぶなど、天気がこれだけ社会的な影響を及ぼすのかを痛感した年でした。
一方、翌年になると、一転、夏は猛暑となり、最高気温が40℃を超える観測地点がでる等、この先天気はどうなってしまうのだろうと、天気への関心がさらに高まりました。
まさに「転機」の年となったと思います。
Q2 平成の地震・火山災害の中で特に印象深かった災害は何ですか?
その時は東京勤務で、外出中に地震が発生し帰宅困難者に。当夜は外出先で一夜を過ごし、得られる情報も少なく不安な一夜を過ごしました。
翌朝、得られた情報から規模の大きさがわかるにつれて、体の震えが止まらなくなりました。
この時の自分の大変さなどとてもちっぽけなもので、この時から自分はなにができるのかを考えるようになりました。
ただ、まだ還元できるものが少なく、今もなにをすべきかについては継続して考えています。
Q3 平成30年間における世間の防災意識に変化はあったと思いますか?
ただ、知りえた情報は自分のいる場所とは違う世界で起こっているのではと、他人事のように思っていることが多いのではないでしょうか。
また、「起こったこと」は伝わってきますが、いざという時にどうすれば良いのかが理解されていない気がします。
大規模災害発生時は、自分でなにができるかを整理しておく必要があると思います。
Q4 次の元号「令和」はどんな時代になることを願いますか?
最近、学生の「理科離れ」が進んでいると聞きます。小学校の校庭に、百葉箱もない所があるらしいですね。
伝えていく側の立場として、いかに幅広く理解を深めていけばよいのか、また、いろいろな思いや立場などの様々なニーズにどう答えていくべきなのだろうか考えなければなりません。
これからは、AIでできることと人がやるべきことのすみ分けがなされ、万人に満足のいくサービスが展開されることを期待したいです。
※「気象予報士」は、平成6年に導入された「気象予報士制度」により定められた国家資格です。そのため、勤続年数と資格保有暦は異なります。