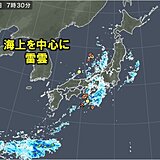<気象予報士が振り返る「平成の災害」③>インタビュー【平松信昭】PR

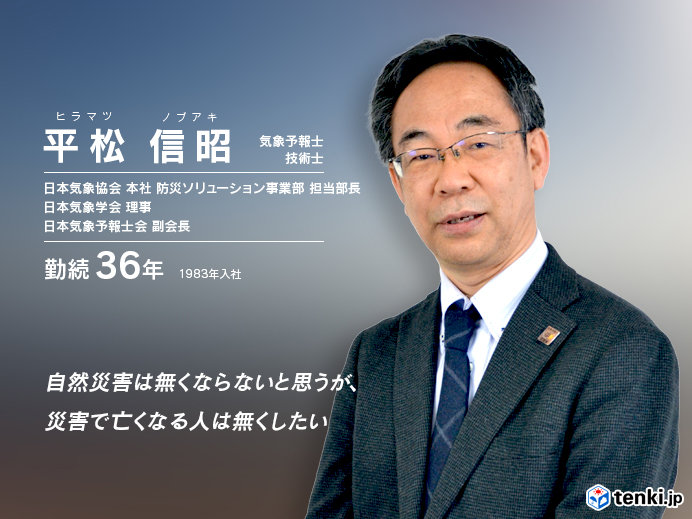
Q1 平成の気象災害の中で特に印象深かった災害は何ですか?
この日は気象学会の天気予報研究会で気象庁に出かけていました。
この研究会は偶然にも、前年(平成25年)の成人式の大雪はなぜ予測できなかったのか、というテーマでした。
研究会の途中に職場から「関東平野でも大雪になりそう」との連絡があり、私はお客様の対応に向かいました。
本格的に雪が降り出すとみるみる降り積もり、高速道路は通行止めになりました。予報では未明から雨に変わるとの予想でしたが、予想以上に寒気が強く、雨になったのは早朝でした。
朝、降り積もった雪は排水溝を塞ぎ、場所によってはくるぶしまで水に浸かって、非常に冷たい思いをして、家に帰ったことが強烈な記憶として残りました。
Q2 平成の地震・火山災害の中で特に印象深かった災害は何ですか?
御嶽山噴火のニュースは、東北地方を旅行中に携帯のニュース速報で知りました。秋の好天の土曜日、多くの登山者が犠牲になっているという痛ましい情報でした。
私も10年前の秋に御嶽山に登っています。天候に恵まれ、噴火があった日と同じように、山頂は多くの登山者で賑わっていました。
火山噴火は地震と違って、ある程度、事前予知ができることが多いので、大変驚き、自然災害に備える難しさを感じました。
Q3 平成30年間における世間の防災意識に変化はあったと思いますか?
土砂災害警戒情報や特別警報のように、災害と直結するような情報が発表され、記者会見も行われるようになりました。
平成の間に、防災情報を提供する側の意識は大きく変わったと思います。
その一方で、情報の受け取り側にはまだまだ課題があります。
「自分だけは大丈夫」という"正常化の偏見"(正常性バイアス)は避難することをためらわせ、逃げ遅れて命を亡くす方はまだまだ多いと思います。
Q4 次の元号「令和」はどんな時代になることを願いますか?
記録的短時間大雨情報が届くと、「この雨は危険だぞ!」と判断することができます。
また、緊急地震速報は、すでに地震による揺れが始まっていても「これは大きいぞ!」と身構えることができるので、地震大国日本に不可欠な情報だと思います。
あとは、防災情報を受け取った後にいかに自分の命を守る行動ができるか、ということではないでしょうか。
そのためにも防災教育を小学校、中学校の頃からしっかり行い、我々が小学校の頃に行っていた火災時の避難訓練と同様、小さい頃から自然災害から自分の身は自分で守ることをしっかり身につけさせないといけないと考えています。
令和の時代も自然災害は無くならないと思いますが、災害で亡くなる人は無くなるように願っています。
※「気象予報士」は、平成6年に導入された「気象予報士制度」により定められた国家資格です。そのため、勤続年数と資格保有暦は異なります。