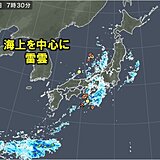<気象予報士が振り返る「平成の災害」②>インタビュー【吉竹顕彰】PR
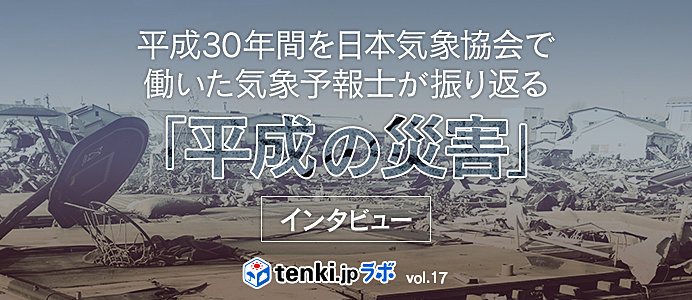

Q1 平成の気象災害の中で特に印象深かった災害は何ですか?
平成29年7月5日、「九州北部豪雨」が発生、福岡県や大分県で甚大な大雨災害になりました。
30年近く放送局で気象キャスターを担当している私は、当日、「線状降水帯が全然動かない」「これは尋常ではない」「危ない!」と判断。
急遽、放送局へ向かい15時過ぎから大雨特設番組で放送を開始。
第一声で「これは記録的豪雨です。きわめて危険な状況です。命を守る行動をしてください。避難をしてください」と呼びかけ、翌6日朝まで大雨の状況と防災対策を伝え続けました。
しかし、実際には多くの人命が失われてしまい、減災にどれだけ貢献が出来たのか反省点も多く、非常に無念でなりませんでした。
さらに平成30年の「西日本豪雨」により広域に甚大な被害が発生、気象庁、民間気象会社、放送局が協力しながら気象情報、防災情報をどう発信していくべきなのかが、改めて問われていることを痛感しました。
Q2 平成の地震・火山災害の中で特に印象深かった災害は何ですか?
平成3年に長崎県にある雲仙普賢岳が噴火、大規模な火砕流が発生、多くの犠牲者を出しました。
平成になって初めて経験した火山災害で記憶に強く残っています。
噴火に伴う火山灰は私が住む福岡市まで到達、噴火が静まるので数年間は、気象情報の中に降灰予想を含めて情報発信を行いました。
平成7年の阪神・淡路大震災後は日本列島各地で相次いで地震が発生、2005年(平成17年)には福岡県西方沖地震で私の住まいも多数の食器が壊れ本棚が倒壊しました。
そして平成23年の東日本大震災、平成28年の熊本地震の被災地では今でも多くの方々が復興に向けてたいへんな生活を強いられています。
Q3 平成30年間における世間の防災意識に変化はあったと思いますか?
確かに防災に対する国や自治体のハード、ソフト両面からの対策は、昭和の時代と比べ格段に進歩しています。
これと同時に、たいへん重要なことは私たち一人一人のそして地域での防災意識の向上と協力です。
例えば、「おばあちゃん元気ね」という普段からの近所の人との声かけや心の触れ合いが防災の原点であり、いざというときにお互い命を救う行動につながります。
今後、自然災害は社会基盤の変化とともにその発生場所や発生形態、規模なども急激に変化多様化し、私たちが想像していない新たな災害も次々に起こることが考えられます。
私たち人間の英知はまだまだ自然の振る舞いには及びません。
自然現象に対しては驕ることなく謙虚に向き合いながら、自然災害のリスクを考慮したこれからの社会創りが大切です。
Q4 次の元号「令和」はどんな時代になることを願いますか?
気温上昇は雨の降り方も変え、平成の時代は豪雨など激しい気象現象が多発しました。
1988年にIPCC(気候変動に関する政府間パネル)が設立され、地球温暖化に対する世界的な取り組みが始まりました。
平成元年はその翌年1989年、まさに平成は地球温暖化に伴うさまざまな影響が現実のものとして次々に表面化、クローズアップされた時代といえます。
今後、さらなる自然災害の増加、変化への対応を考える上で、地球温暖化への対策が喫緊の課題となります。
新しい元号「令和」は、日本の美しい四季や自然と人の心の一体感を表現した「万葉集」から命名されました。
「令和」の時代はまさに日本の、そして世界の気候や自然と人類との共存を真剣に考える時代です。
※「気象予報士」は、平成6年に導入された「気象予報士制度」により定められた国家資格です。そのため、勤続年数と資格保有暦は異なります。