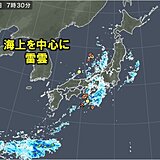<気象予報士が振り返る「平成の災害」①>インタビュー【辻本浩史】PR
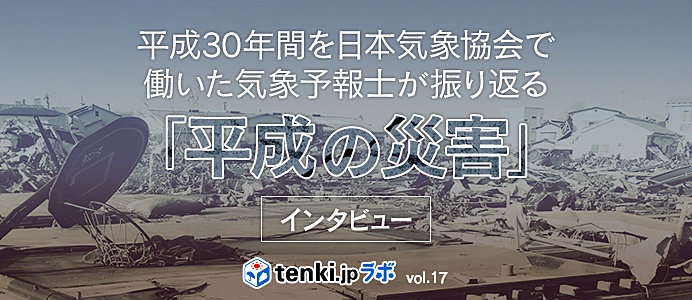

Q1 平成の気象災害の中で特に印象深かった災害は何ですか?
平成24年九州北部豪雨、平成26年広島土石流災害、平成29年九州北部豪雨等の経験をふまえ、防災気象情報の整備(種類、時空間解像度、伝達方法)が一段と進む一方で、高度化する防災気象情報と人間の避難行動心理の乖離も問題となっています。
この災害は、「住民の避難行動」の詳細を徹底的に再分析する事の重要性を行政・学識研究者・気象情報サービス会社へ認識せしめるものとなりました。
Q2 平成の地震・火山災害の中で特に印象深かった災害は何ですか?
隣接する大阪市内のマンションの10階で地震を経験。地鳴りの音で「揺れる前に」飛び起きたのを覚えています。
未曽有の災害直後は、人間も社会も麻痺状態になることを痛感しました。
当日は大阪市内の交通も正常で、関西支社事務所でほぼ通常通りの勤務でした。ただ、神戸市内から煙が立ち上がる様子は、事務所内のテレビで横目で見ていました。
そこで起こっていること(何千人の方が、圧死、焼死しているという事実)をイメージするセンサーに、脳がブレーキをかけている状態となっていました。
Q3 平成30年間における世間の防災意識に変化はあったと思いますか?
国土交通省砂防部資料の「地区ごとに防災に取り組む必要性について」によると、平成30年7月豪雨では「行政が指定する避難所」への避難率は相変わらず少ないものの、「自宅の上階へ避難した」「親戚・知人宅に避難した」のように自らが判断して命を守る行動を取ることができた人も確認されているそうです。
一方で、日常生活の中では「防災」や「避難」を意識する機会が未だに少ないのが課題です。
地域行事や、運動会などの学校行事等における避難訓練の実施や地域・周辺の過去の災害を振り返る場を増やし、かつ、これらの活動がボランティアだけではなくビジネスに組み込まれて継続していくことが重要と考えています。
Q4 次の元号「令和」はどんな時代になることを願いますか?
被災地から線路上を歩きながら淀川をわたり、大阪方面へ食糧・水を求めて歩いてくる人々。多少の物資不足はあるものの普通の日常生活をおくる人々。
近代社会で同時進行する日常・非日常の世界に、言葉では言い表せない無常を感じました。
東日本大震災では、沖合に設置されたGPS波浪計リアルタイムデータの異常とも思われる変化に、これから起こるであろう巨大津波による悲惨な事態を想像して「日本が壊れてしまう」と足がすくみました。
しかしながら災害の記憶はいずれ必ず形をかえていき、ある者にとっては過去の記憶の一つとして薄れていきます。
防災に関して学ぶという究極は、つまるところ「哲学」に足を踏み込むという事です。
※「気象予報士」は、平成6年に導入された「気象予報士制度」により定められた国家資格です。そのため、勤続年数と資格保有暦は異なります。