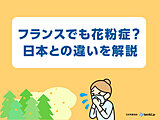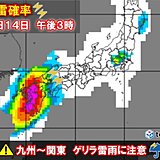さぁ八月! 足の速い夏を逃さず満喫したい! 季節は進み秋の予感も……

「かき氷」暑い中でこそ食べよう!

いつ頃から暑い夏に氷を楽しむようになったのか、と調べてみると意外に古く『日本書紀』の仁徳天皇の記事の中に「熱い月に水や酒に漬けて用いた」と見つけられます。冬の間にできた氷を氷室にしまっておくと夏になってもとけ出さなかったということです。冬にしかできない氷を夏の暑さの中で楽しめる、これは奇蹟に近い感覚だったのではないでしょうか。
平安時代の人々も「かき氷」を楽しんでいたようです。清少納言の『枕草子』に「削り氷(けずりひ)にあまづら入れて、あたらしき金鋺(かなまり)に入れたる」とあり、金属製の器に甘いかき氷をいれたものが、優雅で上品なものとして述べられています。あっという間に溶けてしまう、その儚さもまた優雅と考えられていたのかもしれません。
現代では冷凍技術も発達して何時でも何処でも、楽しくかき氷を味わえる嬉しい時代です。そんな中であえて天然氷にこだわるお店もあります。理由は時間をかけてじっくりできた氷の美味しさだとか。自然が育んだ味わいの魅力は無二のもの、ということでしょうか。
なんといっても「かき氷」は暑い夏の味方、八月も食べ時です。バラエティ豊かな「かき氷」を存分に味わって過ごす、これもちょっといい夏ではありませんか。
参考:
『日本古典文学全集 日本書紀(2)』小学館
『新版 枕草子 上巻』角川ソフィア文庫
この暑さ! だから嬉しいのが「夕立」です

「夕立」の降りの激しさは「滝落とし」や「篠突く雨」などとも表現されます。「滝落とし」には水量の多さが感じられ、「篠突く(篠竹を突き立てる)雨」には雨の勢いの強さが感じられます。
ほかに「銀竹(ぎんちく)」ともよばれます。目の前が真っ白になるほどの雨なのでしょう。銀の竹にたとえるとはなんとも幻想的な雨ではありませんか。「銀竹」は冬には氷柱(つらら)の意味にも使います。
「雨粒の顔に当りてより夕立」 山下美典
「鏡中に西日射し入る夕立あと」 山口誓子
「ゆふ立の過ぐるや森の夕神楽」 蒼虬
夏の風物としての「夕立」の表情がさまざまに見えてきます。昨今はこの風物としての「夕立」に出会うことが少なくなっているような気がします。なによりも雨が大きな被害になりませんように、と祈りたいと思います。
意外ですか!? 秋は八月に立ちます!

アキアカネとともに秋がくる?
耳を澄ませば夏の真っ只中とはいえ、蜩のカナカナカナカナというちょっと切ない鳴き声が聞こえてきませんか。空を見上げてみましょう、雲が流れていくのが見えませんか。微かな風に乗ってアキアカネが山から下りてくるのもこの頃ではないでしょうか。そんな中でしたら少し涼しい風も感じられそうです。しみじみと秋を感じられる涼しさを「新涼」と呼ぶ頃には、新しい秋の到来が見えてきそうです。
「立秋」も末候になると、ところによっては霧がゆったりと立ちのぼることもあるようです。「歳時記」を見ていくと、八月は暑さの中にも気づかないうちに秋が忍び寄っているのだと気づきます。残り少ない夏は心持ち早足になってきています。後悔のないようにお楽しみリストをもう一回チェックしておきましょう。そうすれば秋を迎える心にも余裕ができるのではないでしょうか。