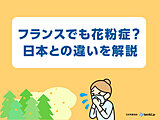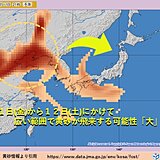ツーンっと鼻に抜ける「わさび」の刺激! 雪解けの清流があってこそ!?

人類より早い!?「わさび」が日本にやって来た!

「わさび」の正式な学名は「Eutrema japonicum」です。「日本」の国名が入っているように、日本の固有種ということがわかります。別名として「Wasabia japonica」も使われており、ここにも「わさび」と「日本」が入って日本独特の植物と感じることができます。
このように古くから日本に存在した「わさび」ですが、生育地が山奥といったあまり人目につかないところだったため、早くから多くの人に用いられることはなかったようです。
食べ物として文献に多く登場するようになるのは室町時代。今に伝わる和風の様式、和室のしつらえや茶道、華道といった日本文化が成立していた頃と重なります。その頃はどのように「わさび」が食卓に供されたのでしょうか。
参考になるのはお寺や神社、また貴族が書き残した記録です。特におもてなしのために購入した食材の記載は残すべき重要事項だったのでしょう。その中に「わさび」の記述が現れるようになり、食材として使われていたことがわかります。
「四条流庖丁書」は室町時代の料理書ですが、この中の刺身の記述に「鯉はワサビ酢、鯛にはショウガ酢」というものがあり、わさびやショウガが調味料として酢と合わされ、素材により使い分けられていたことがわかります。わさびは生魚の他に貝や鳥にも使われていたらしく、料理で利用されることがこの頃には定着していたことがわかります。
みんな大好き「にぎり寿司」と「わさび」の関係は?

上方から江戸へ多くの文化が伝えられて来ると、やがて江戸でも新たな文化が作られ始めます。食においても変化が起きていきました。客がお金を支払うことで自由に料理を楽しむ文化が成立していったのです。
食材についても、定置網漁法の発達によってマグロが本格的に獲れるようになったこと。また上方から運ばれてきた醤油が江戸周辺で作られるようになったことが挙げられます。このふたつが揃ったことでマグロを醤油に漬け込む「ヅケ」の方法が浸透し、「刺身にわさび」だった食べ方に醤油が加わったことになります。
「わさび」「まぐろ」「醤油」の三拍子そろったタイミングにぴたりと合ったのが、マグロの大衆化です。
マグロの大漁がきっかけとなり庶民の食べ物として広がっていきました。それほど上等な魚とされていなかったため売れ残れば捨てられる運命。捨て場に困った挙げ句すしダネとして使ってみたところ、これが大いに流行したといわれています。
「わさび」の普及は、獲れすぎのマグロが庶民の味となっていくのと同時進行だったのです。
「わさび」の魅力ってなに?

「わさび」は決してたくさん食べるものではありませんが、無ければ寂しい味で我慢しなければならない、という料理を奇跡的に美味しくする素材です。程良く効いていれば心地よい美味を堪能できますが、少しでも量が多いとツーンとくる刺激は涙が出るほど、なんともバランスの妙が魅力なのではないでしょうか。
「山葵田を雪の匂ひの水くぐる」 木村里風子
「水清く山葵はかくて人に辛し」 山口青邨
「沢水は春も澄みつつ山葵生ふ」 松本たかし
俳人たちが句にする「わさび」はどれもフレッシュな魅力を湛えています。現在では「わさび」が料理にもたらす効果が注目され、海外でも人気を集めているとのこと。日本には無い食材との取り合わせで発見される、革新的な「わさび」の美味しさもまた、楽しみにしたいですね。
参考:
山根京子『わさびの日本史』文一総合出版
渡辺善次郎『巨大都市江戸が和食をつくった』農村漁村文化協会
『ブリタニカ国際大百科事典』