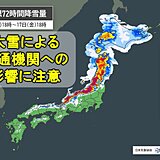~パリに終わりはない~ ヘミングウェイの遺作にして青春の書「移動祝祭日」

7月2日は、ノーベル賞作家ヘミングウェイの命日。今回ご紹介するのは、彼がパリで過ごした若き日の修行時代を綴った著書『移動祝祭日』です。2015年11日13日に起こったパリの同時多発テロ事件後には、「抵抗のシンボルの本」となりフランスでベストセラーを記録しました。本書が発表されたのは1964年、ヘミングウェイの死後のことで事実上の遺作といわれています。50年以上の時を経て今なお人々に勇気と希望を与える、ヘミングウェイのパリの日々を味わってみましょう。
実生活もハードボイルド!ヘミングウェイの生涯

ヘミングウェイ博物館(アメリカ・キーウエスト)
高校卒業後、新聞記者の見習いを経て第一次世界大戦に赴きますが、全身に爆弾の破片をあびるという重傷を負うことに。戦後は記者としてパリに滞在、新聞記事を書きながら小説の執筆をはじめました。『移動祝祭日』は、この頃のパリでの日常を綴った青春の記念碑的作品です。
パリでの日々の後、1930年代にはスペイン内戦に人民戦線側として積極的に関わり、第二次世界大戦ではキューバでファシズムに対抗する活動を展開するなど、まさにハードボイルドな人生を送ります。
1954年にはノーベル文学賞を受賞するも、同年に2度の航空機事故に遭いながら奇跡的に生還。晩年は数多く経験した怪我や事故により、躁鬱症状に悩まされたといわれ、やがて執筆活動にも影響を及ぼすようになっていきました。1961年7月2日早朝、ヘミングウェイは猟銃により自らの命を絶ちます。61年の波乱に満ちた生涯でした。
文豪がみずみずしく綴る、パリでの「魂の祝宴」の日々

『移動祝祭日』巻頭のエピグラフには、ヘミングウェイが晩年に親交を結んだホッチナーというライターに語った言葉が記されています。『移動祝祭日』というタイトルは、ヘミングウェイ自身によるものではありません。彼が世を去った後に、この言葉に感銘を受けたホッチナーの助言でヘミングウェイの最後の妻メアリーが決めたのです。
移動祝祭日(A Moveable Feast)とはキリスト教の用語で、その年の復活祭の日付によって移動する祝日のこと。もうひとつは、どこにでもついてくる饗宴、「魂の祝宴」といった捉え方があります。ヘミングウェイにとって、パリは生涯にわたって消えることのない輝かしい魂の記憶だったのですね。
『移動祝祭日』は、最初の妻ハドリーと生活しながら文学修業をしていた1920年代のパリが舞台。第一次世界大戦の傷を癒した22歳のヘミングウェイが、行きつけのカフェでひとり執筆に没頭し、ガートルード・スタインやスコット・フィッツジェラルドといった芸術家たちと交流しながら、自らの文体を確立していくさまが生き生きと描かれています。
冒頭のカフェでの執筆の描写は、まるで自分も同じ空間にいるような感覚にとらわれます。カフェに現れた美しい女性、ラム酒、白ワイン、牡蠣の味、一編の小説を書き上げる疲労感、その後に訪れる悲しみと喜び。その瞬間のすべてを創作に注ぎ込もうと葛藤する、純粋さと力強さに満ちた若者の姿を間近に感じ、誰もが心打たれることでしょう。
ヘミングウェイの著名な作品には、戦場、闘牛、海といった冒険的要素が多く盛り込まれています。男性的な作風から、アメリカのハードボイルド小説の基礎を築いたといわれています。
人生の終わりを前に、ハードボイルドな世界から離れ、30年前のパリでの日常をノスタルジックに描いたヘミングウェイ。希望に満ちた若き日を回想しながら執筆することは、心身ともに傷を負った晩年の彼の心を穏やかに満たしたのではないでしょうか。
誰の心にもある!終わりがなく、いつでも帰れる場所

『移動祝祭日』の結びの章「パリに終わりはない」で、ヘミングウェイはこのように語っています。
小説や映画のなかのセーヌ川、エッフェル塔、モンマルトルは、今も変わらずパリにあり、人々の日常生活の舞台でもあります。パリは決して過去のものではなく、さまざまに変化しながら、現在を経て未来へと終わりなく繋がっていくのです。
テロで心に傷を負ったパリの人々を勇気づけた『移動祝祭日』。ヘミングウェイは、誰の心にもある「魂の祝宴」は決して過ぎ去ったものではなく、いつも私たちと共にあることを教えてくれます。
参考文献
ヘミングウェイ/高見浩 訳『移動祝祭日』新潮文庫 2009