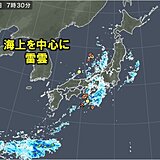<気象予報士が振り返る「平成の災害」⑥>気象災害(平成11年-平成20年)PR

このうち平成11年~平成20年に発生した7つの気象災害について解説します。
【平成11年8月】玄倉川水難事故
神奈川県玄倉川では、キャンパーが濁流に流され13人が死亡したほか、各地で河川の急激な増水や、土砂崩れによる被害が発生しました。
当時は、最大風速17m/s以下の熱帯低気圧は、台風を含めた広義の熱帯低気圧と区別するために「弱い熱帯低気圧」と呼び、この熱帯低気圧も「弱い熱帯低気圧」でした。
しかし、この「弱い」の表現が防災体制を緩めたのではないかとの反省から、翌年から台風の強さや大きさの階級で「弱い」、「小さい」、「並」などを廃止しました。
【平成12年9月】東海豪雨

豪雨により道路が浸水したようす(出典:中部地方整備局庄内川河川事務所ホームページ)
名古屋市やその周辺の市町村では堤防の決壊や河川の氾濫により、広範囲で浸水害が発生したほか、各地で土砂災害も発生しました。
この豪雨をきっかけに、平成13年6月に水防法が改正され、浸水想定区域制度が創設されました。この制度により、都道府県管理河川にも洪水予報河川※の指定を拡大し、洪水予報河川を対象に浸水想定区域の指定・公表が義務付けられました。
(※国土交通大臣又は都道府県知事が、流域面積が大きい河川で洪水により国民経済上重大な損害を生じるおそれがあるとして指定した河川)
【平成16年9月】平成16年台風18号

台風により街路樹が倒れたようす
瀬戸内海沿岸や、西日本から北日本にかけての日本海側沿岸などで高潮となり、広島県の厳島神社では暴風と高潮により国宝18棟と重要文化財12棟が損傷し、修復費用は7億9000万円に上りました。
札幌市では、暴風により北海道大学のポプラ並木をはじめ街路樹が倒れ、市内の街路樹の3000本以上の倒木が確認されました。
平成16年は、この台風18号を含めて日本列島への台風上陸数は10個となり、この上陸数は過去最多となっています。
【平成17年12月】羽越本線特急列車脱線転覆事故
JR東日本はこの事故を受けて、JR東日本研究開発センター内に防災研究所を設立し、また、列車運休に関わる風速規則を強化したり、防風柵を増設したりするなどの対策を行いました。
また、風速計で捉えることが困難だった突風の早期探知を図るために、竜巻に伴う渦を直接捉える手法として、JR羽越本線余目駅にドップラーレーダーを設置し、事故の再発防止に努めました。
【平成18年11月】北海道佐呂間町の竜巻

竜巻により倒壊した家屋のようす
突風による飛散物は、標高差では被害域より100m以上高く、水平距離では北に約15㎞離れた所でも確認されました。
気象庁は、平成17年、18年と発生した竜巻災害を契機に、竜巻などの激しい突風に関する予測情報の技術開発を加速し、平成20年には「竜巻注意情報」、平成22年には「竜巻発生確度ナウキャスト」の発表を開始しました。
【平成17年12月~平成18年3月】平成18年豪雪

平成17年12月~平成18年3月の積雪の深さ(出典:気象庁ホームページ)
3月にかけて降雪量は山沿いを中心に平年を上回り、屋根の雪下ろしなど除雪中の事故や倒壊した家屋の下敷きになるなど、全国で152人が亡くなるという大きな被害が発生しました。
高齢者の犠牲者が多く、山間地区での過疎高齢化の問題を露呈することとなりました。
気象庁はこの豪雪を「平成18年豪雪」と命名しました。
豪雪で命名されるのは、「昭和38年1月豪雪」以来、43年ぶりでした。
【平成20年7月】都賀川水難事故
上流で降った大雨により、都賀川の水位はわずか10分間で約1m30cmも急上昇し、川遊びをしていた児童を含む5人が増水した川に流されて亡くなるという事故が発生しました。
事故の被害を拡大させた原因のひとつとして、当時周辺地域には大雨・洪水注意報や警報が発表されていたのにも関わらず、河川を利用する人々に十分に伝わっていなかった、ということが挙げられました。
そのため、都賀川には、大雨洪水警報および大雨洪水注意報が発表された時に点灯する回転灯が設置され、局地的な大雨による災害への対策がとられました。