8月2日は『ハブの日』。ハブの生態や咬まれた時の対処法について知ろう

イメージ画像
1.ハブには数種類が存在する
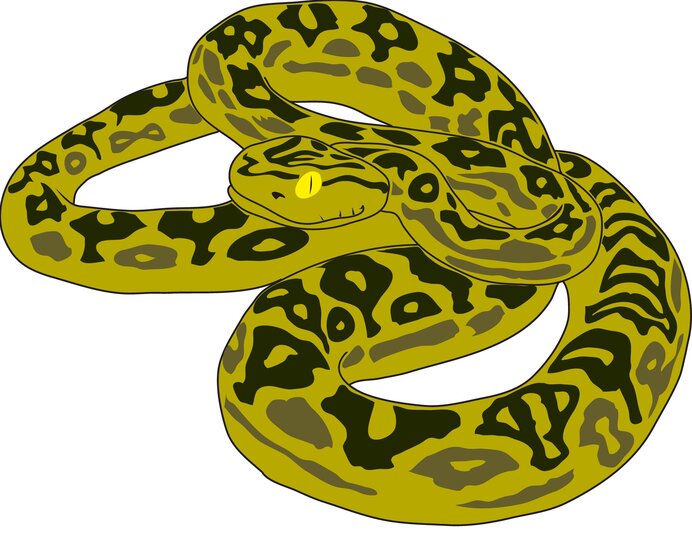
イメージ画像
また、ホンハブ以外にもトカラハブ、ヒメハブ、サキシマハブ、タイワンハブといった種がいます。トカラハブはトカラ列島の中でも宝島と小宝島にのみ生息し、ヒメハブは沖縄諸島と奄美群島のみに生息。どちらも比較的毒性が弱いのが特徴です。また、サキシマハブは八重山列島固有のハブで、タイワンハブは台湾原産でサキシマハブに似ています。両種とも本来は沖縄本島にいませんでしたが、人の手によって持ち込まれ、現在では沖縄本島でも野生化しています。
2.ハブの生態を知れば危険を回避できる

イメージ画像
ハブは辺りが薄暗くなってくると活動を開始し、湿度が高く暖かい夜には特に活動的になります。そしてネズミ(ドブネズミやクマネズミなど)やカエルを好んで捕食し、稀にウサギやネコなどの哺乳類や鳥類も捕食します。獲物に対しては体をしならせてから頭部を突き出して咬みつきますが、ジャンプをすることはできません。したがって、ハブに対して約1.5m以上の距離をとれば攻撃は届かないとされています。ハブを見つけたらとにかく2m以上離れるのが鉄則です。
3.やっぱり怖い!ハブの毒

イメージ画像
こうしたハブ毒の被害に古くから悩まされてきた沖縄県では、数十年かけてハブ対策を進めてきました。ハブ毒の血清を県内の医療機関に常備させているほか、ハブに咬まれた際の対応法などを子供の頃から教育しています。その結果、沖縄県では2011年~2020年の10年間でハブ毒による死者を0に抑えています。また、ピーク時には年間300~500名程がハブに咬まれていましたが、ここ10年間は毎年70名前後の被害で推移しており、咬まれること自体が少なくなっています。
4.それでもハブに咬まれてしまったら

イメージ画像
1.咬まれたらまずは慌てずに、ハブかどうかを確かめます。ハブと無毒のヘビを見分ける方法として手っ取り早いのが、頭部のうろこの形状確認。ハブの仲間の頭は細かいたくさんのウロコで覆われており、無毒のヘビは大きなウロコでおおわれています。また、ヘビの種類が分からなくても、ハブであれば咬まれた牙の跡が2本あり、数分で患部が腫れてものすごく痛みます。
※牙の跡が1本あるいは3~4本の時もあります
2.ハブに咬まれたら大声で助けを呼び、すぐに医療機関を受診します。パニックになって走って病院に行こうとすると毒の回りが早くなるので、可能であれば誰かに車で運んでもらいましょう。周囲に人がいない場合は心拍数が上がらないよう、ゆっくり歩いて向かうようにします。
3.病院まで時間がかかる場合は包帯やネクタイなど、帯状の幅の広い布で指が1本通る程度にゆるく縛ります。血の流れを減らしつつ、15分に1回はゆるめるようにしましょう。恐怖心から細いヒモなどで強く縛るのはNG。血流が止まってしまうので逆効果になります。
上記の3点を知っておけば、重篤化や後遺症が残ることも少なくなるとされています。
人間と動物の共存

リュウキュウアオヘビ


















