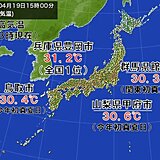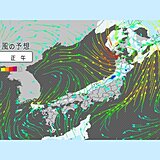夏の終わりに没した日本最大の大怨霊「崇徳院」。その本当の姿とは?

生きながら怨霊になったとされる崇徳院。けれどもその実相は?
崇徳院は、世にいう日本三大怨霊の一柱に数えられ、今なお怖い怪異譚を新たに生み出しています。しかし遺された御製の和歌は小さな命に心寄せる優しさをたたえたもの。崇徳院は本当に大怨霊だったのでしょうか。
院政が生み出した呪われの皇子・崇徳院の生涯

崇徳院廟。崇徳院が進んで人に仇なそうとした記録は何一つありません
治暦四(1068)年即位した後三条天皇により凡そ100年間続いた藤原氏による摂関政治(幼帝を立て、補佐役の臣下摂政・関白が政治の実権を掌握する政治体制)は実質終わりをつげ、後三条帝の意思を継いだ白河天皇が譲位後も政務を取り仕切って、上皇(太上天皇)による政治支配を特徴とする院政時代が始まりました。
白河上皇(後に受戒して法皇に)の院政下にあり天皇に即位した一人が鳥羽天皇で、白河院の孫にあたります。白河院には出自の怪しい祇園女御なる愛妾がありましたが、この祇園女御に、父を七歳の時に亡くした藤原璋子(ふじわらのしょうし)を養女として預け、自身も代父となって孫の鳥羽天皇の后として入内させます。この璋子の産んだ第一皇子が顕仁親王、後の崇徳院でした。
ところがこの璋子は白河院のお手付きの愛人であったため、皇子顕仁の本当の父は白河院であると人々は公然と噂し、父の鳥羽天皇もまたそれを信じて顕仁親王を憎み、疎みました。そして白河院は鳥羽帝を退位させ、保安四(1123)年には当時五歳の顕仁親王(崇徳天皇)を即位させてしまうのです。
治天の君こと白河院にいいようにされてきた鳥羽上皇ですが、白河院が崩御すると、いよいよ自身の院政政治で権力を振るい始めます。
鳥羽上皇の寵姫に保延五(1139)年に男子が生まれると、2年後には当時23歳の崇徳天皇を退位させ、幼い躰仁親王(近衛天皇)に帝位を践祚(せんそ)。さらにこの幼帝が十代で夭折すると、崇徳院の実弟である雅仁親王(後白河天皇)を帝位に。兄弟の即位は、自身の実子の帝位の道が断たれたことを意味し、崇徳院はこのとき実質政治権力の埒外にはじきだされたのでした。
鳥羽法皇の院政下で、権力を再び掌中にしようとする摂関家による暗躍が活発化する中、鳥羽法皇が病に倒れます。後白河院を抱き込んでの権力掌握を目論む摂関家にとって、後ろ盾の鳥羽法皇の危篤は、排除したはずの崇徳院の勢力の盛り返しを危惧させました。
そこで後白河院勢は近衛天皇の崩御は崇徳院の呪詛であるという中傷を流しました。さらに臨終の床にある鳥羽法皇の見舞いに訪れた崇徳院に、面会すら許そうとはしませんでした。
こうして鳥羽法皇が崩御すると、崇徳院と実弟の後白河院との対立は一気に抜き差しならないものとなったのでした。

豊かな感性と教養に恵まれていた崇徳院。その歌は優しさにあふれています
この反乱(実質的には朝廷ー後白河院勢による弾圧粛清)は武士集団、特に平清盛の台頭を招き、連綿と続いた王朝政治の終焉を招いた事件となりました。
投降した崇徳院は四国讃岐に配流となり、二度と京都に戻ることはできませんでした。『保元物語』(作者不詳 13世紀ごろ)によれば、配流地で崇徳院は乱により命を落とした者の慰霊のため、自らの指先から取った血をもって五部大乗経を書写し、京都の石清水八幡宮に奉納するよう使者に託しました。しかしその経には呪詛が込められていると後白河院は恐れ(実際血で書いた経文は気味が悪いものですが)、讃岐に送り返してしまいます。父法皇の臨終にも立ち会えなかったこともあいまって、崇徳院の悲憤は遂に限界を超え、「この上は我、大魔縁となりて、皇を取って民となし民を取って皇となさん」と王朝を呪う言葉を舌先をかみちぎった血により書き記し、後は蓬髪となって生きたまま怨霊悪鬼と化した、と伝わります。
崇徳院は長寛二(1164)年、讃岐で崩御します。諡号(天皇が死後に贈られる正式な天皇名)は侮蔑の意を込めて異郷の地名「讃岐」とされました。後白河院は喪に服することもなく、崇徳院(讃岐院)は配流地の讃岐白峯に葬られたままでした。
その状況が変わったのは、死後11年経った頃、後白河院の最愛の女御である平滋子が死去。続いて中宮(皇后・皇太后・太皇太后の総称)、そして二条天皇の皇子六条天皇(既に譲位して上皇に)の死去が相次ぎ、この頃からこの相次ぐ不幸は何者か、いや間違いなくあの無辜の崇徳院の怨霊による災禍であるという噂がささやかれていました。
さらに都の三分の一を焼失させたといわれる1177(安元三)年の安元の大火、翌1178(治承二)年の治承の大火と災害が相次ぎ、朝廷は浮足立ちます。
既に朝廷はこの頃、平清盛により院政を骨抜きにされ、権力を握られていましたが、その清盛にも不幸が相次ぎます。1179(治承三)年には娘の盛子、さらには嫡子重盛が急死。そしてその2年後には清盛自身が病没します。
朝廷は、崇徳院の呪いを鎮めるために讃岐で法要を行い、また諡号も「讃岐」を「崇徳」に改め(実際に崇徳院となるのはこのときから)、京都のゆかりの地に慰霊廟を建てるなどなどの慰霊に努めました。しかし決してその御霊を京都に戻すことはありませんでした。
崇徳院の京都への帰還が果たされたのは、明治天皇により京都上京区に建設された白峯神宮に本尊を遷座した慶應四年の崇徳院の命日、何と明治改元の前日のことでした。
王朝末期の抒情詩人。崇徳院の歌の世界

崇徳院地蔵、通称「人喰い地蔵」が安置される積善院
瀬をはやみ 岩にせかるる滝川の われても末に 逢はむとぞおもふ (詞花和歌集)
この歌、初出の『久安百首』では「ゆきなやみ 岩にせかるる滝川の」となっており、「瀬をはやみ」としたのは崇徳院自身による改変であろうと思われます。急流は岩にぶつかって二つに分かれてしまっているが、引き裂かれた二つの流れはいつか再び一つになるであろう、という強い意思に貫かれた清冽な印象を与える歌。仲を引き裂かれた男女の激しい恋情の歌として解釈されるのが一般的ですが、崇徳帝の悲劇の生涯を見るにつけ、さまざまな解釈が可能な意味深な内容です。
花は根に鳥はふる巣にかへるなり春のとまりを知る人ぞなき (千載和歌集)
春咲いた桜はやがて根に戻り、鶯は故郷に戻るのに、春という季節の帰るところはあるのだろうか、という抽象的なメタファーが独特で、個性的な一首です。
晩春の日暮れ、各家に灯がともる、心うずくひととき。鳥も人も皆温かい家へと帰っていく。けれども「私には帰宅を待ってくれている家などどこにもない」と、実の親に憎まれ続けた崇徳院は自身の悲しい境遇を「春」にたくしたと解釈することができます。
このごろの鴛鴦(をし)のうき寝ぞあはれなる 上毛(うはげ)の霜よ 下のこほりよ (千載和歌集)
近頃の寒い季節にオシドリが水に浮いて寝ている姿が不憫だ。羽には霜がつき、足元は凍っているではないか。凍えながら耐える野鳥のオシドリに心を寄せる一首です。
「霜よ」「こほりよ」と畳みかける重韻は、現代詩やポップスの歌詞にも通じる、現代人にも訴求力のある名歌ではないでしょうか。
恋ひ死なば 鳥ともなりて 君がすむ宿の梢にねぐらさだめむ (久安百首)
鳥となって愛する人のところへ飛んでいきたい、というモチーフは、古今東西共有されてきたものです。崇徳院の和歌はこのようにけれん味がなくわかりやすいものが多く、本来明るく、素直な心根の人物であったことをうかがわせます。
それにしても、「ねぐら」「ふる巣」「帰る」「うき寝」など、心休まる帰るべきところに安らいたい、という切ない願望が随所にあらわれ、胸をつかれます。
秋ふかみ たそかれ時のふぢばかま 匂ふは名のる心ちこそすれ (千載和歌集)
秋の黄昏時、薄闇の中で、フジバカマの花の香りがにおってくる。まるでフジバカマが私はここよ、と語りかけてくるようだ、という一首。ささやかで可憐な歌です。
いかがでしょうか。これほど優しい歌を歌う人物が、本当に大怨霊だったのでしょうか。
近代に再び繰り返された崇徳院の呪い?人喰い地蔵の怪

関東での平将門と同様、京都では今なお崇徳院にまつわる怪異が
しかし、室町期の応仁の乱の騒乱などで廟は荒廃、廃絶。唯一本尊となる地蔵尊のみが修験者(霞衆)の総本山である聖護院の広大な森に移動され、安置されたと伝わります。当時の京都は地蔵信仰と六地蔵巡りが盛んで、崇徳院ゆかりの一帯にも多くの地蔵の野仏が安置されていたようです。
現在では京都大学・京大病院の敷地になっているこの地で大正時代、京大理学部建設の折に五十体ほどの古い地蔵菩薩の石像が出土しました。
工事人足たちが「地蔵さんじゃ漬物石にも使えない」と、路傍に放り出して休憩の椅子代わりにするなどの粗雑な扱いをしていたところ、やがて工事請負業者の社長や人足、建物の大工の棟梁、出入り商人、大学の建築部長などが相次いで急死する事態が発生。誰ともなく「石地蔵をぞんざいに扱うから祟られたのだ」と噂が広がり出したのです。
有名な稲荷下げ(民間の霊能力祈祷師)に伺いを立てると、「地蔵様の本地仏である大日如来が大変なお腹立ちで、このままではなお六人の命が取られる。それから地蔵には霊力のある狸の霊も憑いている(崇徳院の死没地讃岐は狸霊の本場です)ので、すぐに地蔵菩薩と狸を丁重に祀り、毎日供物を欠かさないよう」と諫言されます。
しかし、それを聞いた大学側の教授は非科学的だと取り合いませんでした。するとその教授が4~5日後に突然亡くなってしまいます。
こうなってくると大ごとだと、大学側も出土した石地蔵を全て並べて祠を設置し、地蔵盆の八月二十八日には盛大に例祭を行うこととしました(『天狗の面』)。
それに先立つ明治末期、現在京大理学部キャンパスのある聖護院吉田村の畑で石地蔵が出土、その地蔵を庭石代わりにしていたところ、その一家全員が亡くなるという出来事が発生。大正末期に地蔵は京大病院敷地内に祀られました。
これらは現在、京大病院と京大医学部の敷地にそれぞれ「祟り地蔵」として祀られています。そしてそれらのすぐとなり、東大路通を挟んだ聖護院の一院家である積善院凖堤堂には、崇徳院地蔵、別名「人喰い地蔵」が祀られています。「すとくいん」をもじり、いつしか人の命を喰らう「ひとくい」へと変質したと伝わります。これらの地蔵は崇徳院を祀る崇徳天皇廟、その信仰圏の民間の地蔵が散逸し埋もれたものだと考えられます。
病院や学校という怪談が生まれがちなシチュエーションということもあるのか、戦後にも猟奇的な事件が発生したり、怪異現象の起こる場所として有名でもあります。京都の人々にとっては崇徳院はなお生々しい恐ろしい祟り神「御霊」として、恐れられているのです。
けれどもその実像は、残された御製の歌の数々、そして薫陶を受けた僧・西行の挽歌などを見ても、並み外れて繊細で心優しく、また才に恵まれた魅力的な人物であったと読み取ることができます。
本当に怖いのは、排除した者を怨霊として悪鬼化し、遠ざける側の猜疑心なのかもしれません。
(参考・参照)
保元物語 日下力 角川書店
天狗の面 (春陽堂文庫 ; 大衆文學篇) - 国立国会図書館デジタルコレクション
崇徳院地蔵 - 源平史蹟の手引き