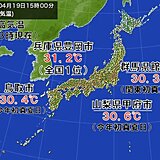待ったなしのごみ問題から地球と未来の子供たちを救うには?5月30日「ごみゼロの日」

新夢の島(15号地)。ゴミの舞う風景は、昭和の怪獣ドラマ「帰ってきたウルトラマン」でも登場しました
「ゴミ」と都市。切っても切れない腐れ縁?

江東区永代橋。この煌めく都会の風景の場所は、江戸時代にはゴミ捨て場でした
自然の環境収容能力を超えた生体が密集状態となる場所、つまり人間の作る「町」「都市」という環境が作り上げられてはじめて「ゴミ」が生じます。逆に言えば、都市は必然的にごみ問題を抱えることになります。
メトロポリスが文明発祥地に形成された時代から、都市は大量のゴミを排出しました。メソポタミアでは、家の建材や食器などの土を焼いて作ったレンガや陶器が大量に捨てられ、廃棄物の上にまた家や都市を建てるので、次第に街の標高が高くなっていく、という現象が見られたそうです。都市は、過去の「ゴミ」を下に押しつぶしながら代謝を繰り返して成長したのです。
そしてごみ問題で避けて通れないのが、人がいやおうなく出さざるをえない屎尿(しにょう)問題です。古代人が犬を共同体の伴侶として選んだのも、食糞の性質を持つ犬が屎尿処理に好都合だったからだ、とも言われています。
牧畜と農業とでサイクルを繰り返すヨーロッパ型の三圃式農業では、家畜の排泄物が肥料となり、都市の屎尿は不要だったため、中世以来屎尿処理はヨーロッパ人を悩ませてきました。日本の場合は、都市(江戸や大阪、京都、また大規模な城下町など)の屎尿は農村に運ばれて下肥(しもごえ)として使用されていたので、長らく屎尿問題はほとんど発生しませんでした。江戸時代には、幕府の置かれた江戸は当時、世界でも指折りの大都市に成長しましたが、農村の下肥の需要に大江戸の屎尿量が追いつかず、屎尿の買い取り価格が高騰して、武蔵・下総の農民が価格抑制を直訴する、などという騒動すら発生しています。
また紙や衣類、鉄くず、燃やした灰に至るまでリサイクルするシステムや、壊れても何度も修理して使い倒す習慣もあり、ゴミの発生は人口に比して抑制されていました。それでも生活用具や廃建材などのゴミは発生したため、幕府は町ごとに「大芥留」(おおあくたどめ・ゴミ集積場)を設け、江戸前期には永代浦(現・江東区富岡八幡宮近辺)を、江戸中期には深川越中島(江東区越中島付近)や猿江木材蔵跡入掘(江東区猿江)を最終埋立地としてゴミを埋め立てました。
江戸でも上方でも、廃棄物を土に埋め、土地をならしてその上に新たな都市を建設する、ということを繰り返しました。海沿いの浅瀬にゴミを廃棄し、水が下がってくると埋立地として整備し、新しい町を建設していったのです。
近代にはじまる大量消費社会と公害は、未来に向けて加速する

大量消費社会が世界中にひろがり、ゴミの量も加速して増えています
そして戦後、農業に化学肥料が投入されるようになると、不要となった屎尿の処理問題がいきなり浮上したのです。
更にアメリカ式の大量消費社会への転換とともに排出されるゴミの量も、かつてとは比較にならないほどふくれあがります。生産活動で生じる工場廃液も垂れ流しだったので、都市近郊の海は漂着ゴミとヘドロで悪臭を放ち、多くの地域で遊泳が禁止となりました。
昭和32(1957)年からはじまった江東区沖の東京湾の埋立地の最終処分場「夢の島」は、当初埋め立てや焼却もしていないゴミをそのまま野積みにしていたため、大火事が発生したり、ハエやネズミの大量発生が起きるなど、さまざまな社会問題が生じました。現在はきれいな公園に整備されていますが、かつての見渡す限りのゴミの山の風景は、つとに有名ですよね。
現在、世界は人口増加と急速な都市化により、廃棄物の年間発生総量は、2016年でおよそ20億t超だったものが、2050年ごろには34億tにまで膨れ上がると予測されています。高所得国の先進国では世界人口のわずか15%程度なのに、世界の廃棄物の1/3以上を排出しています。これに加えて、アジアや大洋州、アフリカなどの新興国の出す廃棄物も今後2~3倍に増加すると考えられます。
生態系や生物生存の阻害要因となることが懸念されているプラスチックゴミは、年間2億5,000tもの量が廃棄され、800万tが海に流出しています。いずれ海のプラスチックゴミの総重量は、全世界の海の魚類の総重量をも上回るという、驚くべき試算(2019年環境白書より)も出されています。
リサイクル・リユース運動やプラスチック容器使用規制など、世界でごみを減らす活動は温室効果ガス抑制と歩調をあわせて進んではいますが、現状ではそうした取り組みは「焼け石に水」レベルと言うしかありません。
なぜなら、文明社会ではより平等で便利で安全なインフラや移動手段を構築するためにますます多くの資源を必要とし、発達増殖する電脳社会のネットワーク構築のために多量の電気製品と電気を必要とするからです。
火力発電がたとえ減少しても、鉱物・ガス・液体などの埋蔵資源の需要は増えこそすれ減ることはないでしょう。軽くて再利用可能なプラスチックを禁止にしても、ガラスや紙を使うことは、別のルートでの環境負荷が大きくなるという提言もあります。
人類には、ストローやレジ袋をなくすだけにとどまらない、根源的な変革が求められています。今のような文明社会に生きながらも私たちが環境負荷やゴミを減らすために出来ることが少なくとも二つある、と筆者は考えます。人間の屎尿の処理方法、そして私たち人間自身の体の扱い方です。
都市文明に生きる私たちが出来ることは…二つの提言

美しい海岸を埋め尽くすゴミ。すべて人のなせるわざ
次に「人間の体」、具体的に言えば「死後の人体の埋葬方法」です。現代の日本では、亡くなるとほぼ100%火葬になります。世界的にも、先進国では火葬が主流で、一部で土葬が併用されています。
2019年、アメリカ・ワシントン州で、人間の遺体をコンポスト(堆肥化)する有機還元葬(堆肥葬)が合法化され、今年5月から実施可能となりました。有機還元葬とは、死亡した人体をウッドチップとバクテリアで満たされた専用棺に納め、約3~7週間かけて全身をゆっくり分解して土へと変容させる弔い方です。遺体はおよそ1立方メートル弱ほどの有機質の土となり、遺族や生前の親しい友はこの土を持ち帰り、保存することも庭に埋めることも、任意の場所に堆肥として利用することも可能です。葬儀に使われるエネルギーは火葬の1/8以下、高温炉での焼却による二酸化炭素排出も抑制できます。人間は、地球上でも大型動物の一つです。七十数億人もの人類の多くが燃やされて灰となるか、有用な肥料となるか、地球環境にとっても大きな規模の変化となるでしょう。
昔なら、土葬・水葬・鳥葬などの自然還元葬こそスタンダードでした。有機還元葬はそのワイルドさを取り去って、洗練させたものと言えます。私たち人間は地球生物との有機的な生態系の輪に、再び参入することになります。
また、有機還元葬が弔いとして優れているのは、身近な大切な人が亡くなっても、その人が土となって還った場所から生えている草花や蝶や蜂、鳴き交わす小鳥を見たときに、「彼らの細胞の一部は、かつてあの人だったのかもしれない」と、実感出来ることになることです。これは、残された者にとって、何より慰めになる体験ではないでしょうか?
人間もまた自然の一部である、とよく言われます。でも、そんなきれいごとをいくら並べ立てても、自分たちの排泄物や死んだ後の肉体すら生き物たちに還元することを拒絶した生活なのです。しかし、自分も自分の家族や友人も、その体が死んだら微生物に分解され、やがて他の生物に取り込まれるのだ、と実感すれば、建前の観念論を超えて、自然や他の生物に、共に生態系の輪を作る仲間だという親近感と一体感をもたらし、根本的な意識変革を個人や社会にうながすことになるかもしれません。そしてこのパラダイムシフトは、文明のあり方の大きな転換にもつながるのではないか。そんな未来のビジョンを想像します。

人間も生態系の一部だった昔、人はたとえば蝶に亡き人の面影を見ていたのかも