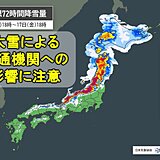カワウソは本当に「魚を祭る」のでしょうか?二十四節気「雨水(うすい)」

どんだけー!宣明暦七十二候に見る「雁」偏愛がすごかった

このうち、「獺祭魚」と「鴻鴈來」はどちらもちょっと一筋縄では行かない「問題あり」の候。どちらも、禮記(らいき)月令(がつりょう)の第六・孟春の一節が原典ですが、まずは、「鴻鴈來」から、何が問題なのか読み解いてみましょう。
「鴻鴈來」は「こうがんきたる」と読み下し、意味は白鳥や雁がやって来る、ということですが、なんとこの「鴻鴈來」、宣明暦七十二候に2回登場します。白露(九月中旬ごろ)の初候も「鴻鴈來」なのです。
更に、寒露(10月中旬ごろ)の初候はほとんど同じような内容と言っていい「鴻雁来賓」(雁が多く飛来する)であり、小寒(1月の初旬~中旬ごろ)の「雁北郷」(雁が北の故郷へ帰っていく)があり、合計4回雁が登場。そのうち3回はやって来る、1回のみが「去っていく」候となっています。つまり、雁は2月下旬にやってきて、9月中旬にまたやってきて、10月の中旬には大挙してやってきて、1月の中ごろ帰って行く。雁に集中してピックアップして並べ、つなげてみると、一体何言ってるんだか意味不明の状態になります。
宣明暦は唐代の長慶年間(821~ 824年)に作られました。唐の都は長安。現在の陝西省の省都西安市に位置します。日本の本州地方よりも寒い、内陸性の気候です。そして、雁や白鳥が多く春から夏にかけて繁殖するシベリア地方と、冬季に渡りをして越冬する南方地域との通り道、雁類の大移動の中継地に当たります。
つまり、1月初旬から中旬の「雁北郷」は、長安付近で越冬した小型のガン類が北の繁殖地へ帰る頃。2月下旬の「「鴻鴈來」は、南の地方で越冬した白鳥、ヒシクイなどの大型のガン類(鴻)や中型の雁が北の繁殖地へ帰るために渡りの中継としてやって来る頃。9月中旬の「鴻鴈來」は、逆に北方から南へ渡る大型のガン類や中型の雁が北から渡りをして来る頃。10月の中旬ごろの「鴻雁来賓」は、長安付近で過ごす小型のガン類と、後発組の南に渡る大型・中型のガン類とが同時にやってきて、長安付近が雁の仲間でひしめきにぎわう、という意味です。表現がややこしい上に、どんだけ雁が好きなんだ、とちょっとあきれるくらいの執着ぶりです。けれども、日本文化にもこうした雁偏愛の感性が共有されていたことは、日本文学での雁の登場数の多さからも、よくわかることではないでしょうか。
獺祭はホントのことだった!カワウソ驚きの生態

大体、宣明暦七十二候を見渡すと、8月下旬の処暑初候に「鷹乃祭鳥」(たかすなわちとりをまつる)、そして10月下旬の霜降初候には「豺乃祭獣」(さいすなわちけものをまつる)という「祭」シリーズが他に2つもあるのです。それぞれ、「鷹が獲物の鳥を捕まえて並べる」「狼が獲物の獣を並べる」という意味で、そのどれもが現実の動物の生態を記したものではなく、何らかの空想もしくは比喩のように思われます。
ところがです。鷹と狼はともかく、カワウソは本当に「獺祭」をするのです。
中国に住むカワウソはユーラシアカワウソ(Lutra lutra)。寒帯のツンドラ地域を除くユーラシア大陸とアフリカの一部という広域に分布する、体長60~70cmほどのイタチ科の哺乳類です。
動物通として知られる漫画家の熊谷さとし氏は、韓国の晋陽(ジニャン)湖というカワウソの保護区にユーラシアカワウソの調査と観察に訪れた際、早朝に二匹のカワウソが川べりで獺祭をしているのを目撃した、といいます。動物園での餌やりの際にも、飼育するカワウソが飼育員が水面に放った餌の魚をキャッチしては、少しはなれた場所の石だたみに並べてはまた餌をもらいに駆け寄る、という行為をすることがあるようで、その様子が映像にも収められています。
ある条件化、つまり周囲に他の捕食者などがおらず餌を横取りされる心配がなく、魚が多く近くにあふれている、などの条件のとき、ことわざそのままの「獺祭魚」をおこなう、ということは確かなようです。大食漢であるカワウソは、水中にもぐったまま餌を食べることは出来ず、岸にあがって食べることになるため、獲っては岸に上がり食べ、また獲りにもどるよりは、ある程度集中して捕獲した後、岸に上がり一気に食べるほうが効率的であるためだと思われます。
その良質の毛皮が乱獲の引き金に…ニホンカワウソの悲劇

江戸時代以前、ニホンカワウソは本土のみならず、離島を含めて全国に多く生息していました。カワウソが日本人にとって身近な野生動物であったことは、タヌキやキツネなどに負けず劣らずさまざまな民話に登場することからもわかります。妖怪の河童は、さまざまな野生生物が見立てられたものですが、亀やすっぽんと並んで、カワウソが河童の正体である、とする説も有力です。水が豊かな日本列島は、カワウソにとっては楽園だったはずです。
ところがそれが明治の開国以降、地獄に変わります。欧米の技術力と経済力に早期に追いつくことを目標にした明治政府は、外貨獲得の輸出品として、日本に生息する多数の野生動物の毛皮に目を付けました。当時欧米諸国は、自国や植民地の毛皮動物をほぼ取りつくし、良質な毛皮を求めていたのです。毛皮の輸出は大きな利益を生み、明治後期から大正にかけて、日本の野生動物は乱獲されつづけました。
また、それに平行して、明治9(1876)年の日朝修好条規を契機とした朝鮮半島への派兵・経済進出、日清戦争、日露戦争と、大陸北部の寒冷地域への出兵にあわせて、防寒防水に特に優れたカワウソの毛皮は大量に軍に徴用されました。こうして、大正時代にはすでにニホンカワウソはほぼ獲り尽くされる状況になっていました。さすがに日本政府も昭和3(1928)年にはニホンカワウソの捕獲狩猟を禁止しますが、実はそれは表向きで、大日本連合猟友会を通じて、国内のあらゆる野生動物、ウサギ、狸、ニホンカモシカ、鹿、クマ、キツネ、そしてわずかに残るニホンカワウソも狩猟し、軍用毛皮として調達していたのです。ニホンカワウソは、他の野生動物と比べて水環境への依存度が高く、移動も少ない動物のため、他の野生動物以上に捕獲されやすく、乱獲に拍車をかけました。
戦後、戦前のように毛皮目的で狩猟されることはほぼなくなりましたが、そのかわり、経済成長による環境破壊、水質汚濁など、さまざまな悪条件がわずかに残ったカワウソたちにダメ押しをしました。こうして、20世紀の半ばには四国をのぞく日本列島全域、四国でも1970~80年代に、ついに日本固有種ニホンカワウソは絶滅してしまったのです。

ツシマヤマネコ
DNA解析でニホンカワウソではない、と判明すると、潮が引くように対馬のカワウソへの世間の興味は薄れていきましたが、ニホンカワウソだけではなく、トキにしろニホンオオカミにしろ、絶滅してから惜しんだり貴重がったりするのなら、どうして絶滅するほどまで追い詰めたのでしょうか。近年はウナギの稚魚(シラスウナギ)の海岸への漂着が激減し、ニホンウナギが絶滅するのでは、と危惧されています。過去に犯した過ちを、今度こそ繰り返してはならないと思います。
対馬におけるカワウソの発見・琉球大学プレスリリース
獺祭をするカワウソ?
コツメカワウソ「獺祭魚」に期待 狭山の動物園 /埼玉