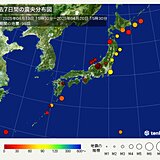家の戸口でコオロギは何してる?七十二候「蟋蟀在戸(きりぎりすとにあり)」

意味は「コオロギが家の戸(玄関)のあたりにいる」というシンプルな内容ですが、なぜコオロギは玄関にいるのか? 何をしてるのか? よくよく考えるとちょっとミステリアスな文言だと思いませんか?
来る…きっと来る…それは段々忍び寄ってきます
この「蟋蟀在戸」とは中国最古の詩篇「詩經」に記載された、農民の暮らしを描いた漢詩『豳風(ひんぷう)』(七月)に由来します。
五月斯螽動股、六月莎雞振羽。
七月在野、八月在宇、九月在戶。
十月蟋蟀、入我牀下。
穹窒熏鼠。
塞向墐戶。
嗟我婦子、曰為改歲、入此室處。(当該部分のみ抜粋)
五月、斯螽(ししゅう・キリギリス、またはバッタのこと)が脚を動かし、六月、莎鶏(さけい・クツワムシ、または鈴虫)が羽を振るう
七月には野原に、八月宇(う・軒のこと)に、九月戸(こ)にいた蟋蟀(しつしゅつ・コオロギ)は、十月、我が牀(しょう・寝台のこと)下に入る
壁の隙間や穴をふさぎ、ねずみを熏りだし、向(まど・窓)を塞ぎ戸口の隙間を土で埋めよう
ああ私の家族たちよ、いよいよやって来る改歳(かいさい・年越しのこと)を無事迎えるために
この居室に籠っていましょう
夏から冬にかけての季節のめぐり、キリギリスやコオロギのふるまいに人間の生活を重ねて叙述しています。面白いのは「蟋蟀」(コオロギ)が、七月(盛夏)には野原にいて、八月(初秋)には家の軒下にやって来る。九月(中秋から晩秋)には家の戸口あたりまで入ってきて、いよいよ冬を迎える十月には「私の寝台(中国の伝統的な生活では床に直接布団を延べる日本と違い、長いすのような寝台「牀几(しょうぎ)」が用いられました)の下にやって来る。」という部分。段々近づいてくるちょっとホラーみたいな表現です。
ここでコオロギにたくされているものは、忍び寄ってくる冬、そして一年の終わりのことなのです。厳しい冬を乗り切るために、秋の終わりには冬支度をしましょう、ということです。
ですから、コオロギが戸口で鳴いている、ということではなく、コオロギが戸口に来るほど冬がせまってきましたよ、という意味なのです。この漢詩に影響を受け、下敷きとした和歌も多く、たとえば
秋ふかくなりにけらしな きりぎりす 床のあたりに声聞こゆなり (「千載集」花山院)
といった歌が知られています。
コオロギとキリギリスが入れ替わった?それはなぜ?

古くは平安時代、枕草子」第五十段「蟲は」では、
鈴蟲。松蟲。促織(はたおり)。蟋蟀(きりぎりす)。蝶。われから。蜉蝣。螢。
とありますが、蟋蟀を「きりぎりす」と読ませ、そしてそれは現代のキリギリスのことではありません。なぜなら、促織(はたおり)と書かれているのが、今で言うキリギリスだからです。キリギリスの「ちょんぎーす」と聞こえる音色を機織の音に見立て、「はたおり」「はたおりめ」という名で呼ばれるようになりました。
つまり、上代から中世くらいまでは、現代で言うキリギリスをハタオリと呼んでいたわけです。ここから、江戸時代に入り博物学や分類学が盛んになりだすと、16世紀初期の正徳年間(1711~1716)ごろより、古典に見られる生き物の分類について、さまざまな議論が巻き起こるようになりました。「和漢三才図会(寺島良安)や「年山紀聞」(安藤為章)など、虫について、時に鳴き声は擬声語であり、どう人が聞きなすか、という主観の問題であり、リンリンと鳴くのは鈴虫か松虫か、チンチロリンと鳴くのは松虫か鈴虫か、の論争にみられるようにこじれにこじれました。古典に見られる虫は具体的に何を指すか、が議論になったのです。
コオロギについても、江戸中期の国学者・賀茂真淵が万葉集所収の「蟋蟀」について、それまで「きりぎりす」と詠まれていたものを「こおろぎ」と読むとという説を唱え、次第にその説が定着していきました。
さらに新井白石は、「古にハタオリメといひしものは、今俗にキリキリスといふ是也。古にコホロギといひしものは、今俗にイトドという是也。古にキリキリスといひしものは、今俗にコホロギといひし是也。(「東雅」1719年・享保4年)」
と記し、今のキリギリスとコオロギは、上代から平安期ごろの呼び名とそっくりいれかわっている、と断言しています。これが正しいとすると、江戸時代中期ごろにはキリギリスの呼び名は、現代と同じキリギリス科の、チョーンギースと鳴く虫を指す、と言うことになり、確かに平安時代と「入れ替わって」います。江戸中期ごろ、鈴虫や松虫、キリギリスを売って歩く虫売りという商売が流行りだし、江戸の町では夏から秋にかけて「ギス籠」(ギス=螽蟖とはキリギリス類の別名)という竹製の虫かごにキリギリスを収めて鳴き声を楽しむ習慣がありました。江戸時代、少なくとも江戸界隈では、キリギリスとは現代のキリギリスだったようです。
ちなみにイトドというのは、現代のオカメコオロギのこと。同じコオロギでも、エンマコオロギやツヅレサセコオロギなどと、オカメコオロギとは別の名で呼ばれていたのだ、と白石は言っています。
けれども、入れ替わるには入れ替わった「理由」があるはず。それはおそらく、コオロギ類とキリギリス類の鳴き声の音色から感じるイメージが関わっていたように思われます。
入れ替わり説と七十二候の背反
生き物の擬声語は、個人でも、時代でも地域でも変化するもので、文化的背景や地域の言語にも大きく影響されます。が、一方でその音質・抑揚・間・音域等によってある程度の方向性はあります。ハトの声を「クックルー」とも「ポッポッ」とも表現しても、「ガオー」とはならないわけです。だからこそ、鳴き声から名づけがされる生き物も多く、そこからある程度の生き物の類推は出来ます。
その意味で言うと、コオロギの音色もキリギリスの音色も「キリキリ」と言う音が不適切かどうかと言うと、微妙。しかし、種類によっては「キリキリ」が適切と思える鳴き声もあるわけです。オカメコオロギとカマドコオロギは、鳴き声が「チッ、チッ」「チリ、チリ」と聞こえることから、これを「キリキリ」と擬声語にするのは不自然ではなく、あり得ることで、コオロギの古名がキリギリスならば、これらのコオロギの鳴き声が語源となり、後に閻魔コオロギやツヅレサセコオロギのコロコロとふくよかで高い鳴き声の印象が取って代わり、コオロギの名になっていったのかもしれません。
一方で、「コオロギ」が擬声語から来ているとすると、キリギリスの平たくにごった音色は「コロコロ」には聞こえません。しかし、鳴き声ではなく、その高い体高と極端に長い足のひざを高く突き上げているキリギリスのたたずまいが、高い軒を掲げた家屋を意味する興梠(こおろぎ・こおろき・こうろぎ)を連想させ、そこからその名がついた、とも考えれば納得できなくはありません。
実際、現代の方言の分布を見ても、東北や北陸の各地、つまり文化政治の中心地から遠い地域に、コオロギをキリギリス、キリギリスをコオロギと呼ぶ地域が多く分布しています。これも、古い時代に呼び名が逆であったことをさしている根拠となります。
けれども、そうだとすると、ここでとある疑問に突き当たります。七十二候の「蟋蟀在戸」は、江戸前期の貞享(1684~1688)暦では「こおろぎ」で、宝暦(1751~1764)暦以降は「きりぎりす」となるのです。たとえば松尾芭蕉(1644~1694)の有名な一句
むざんやな甲(かぶと)の下のきりぎりす
ここで、芭蕉が詠んでいる「きりぎりす」はコオロギのこととされます。芭蕉の時代にはまだコオロギは「きりぎりす」でした。ですから入れ替わりがあったとすると江戸初期から中期ごろが過渡期であるわけで、貞享暦では「きりぎりす」、宝暦暦では「こおろぎ」になるのが道理にかなっています。もっともこの読み方は、さまざまな七十二候の解釈本や、明治期の略本暦などから定着したもので、実際こう読むものであったかは、はっきりしていません。が、ただ何となくそうしたわけではなく、根拠や理由があってそうなっているわけですから、何かしらそこに、単純に「入れ替わった」と、いい得ない何かがあったのです。これは、明治時代の文部省唱歌「蟲のこゑ」の「きりぎりす」が、昭和時代に「こおろぎ」に改変された事件とも関わることです。
漠然とした推測はあるのですが、それについてはいずれあらためて詳しく論じたいと思います。
枕草子
金沢大学・現代方言における「コオロギ」と「キリギリス」