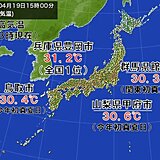今宵12月10日は日本古来のハロウィンナイ!? 2か月に1度の庚申講を知っていますか?

庚申塔、見たことありますよね?
今日12月10日は今年最後の「庚申の日」。でも「庚申講」「庚申の日」って何でしょう。一体夜通し何をするのでしょう。
60日に一度巡ってくる、一番鶏が鳴くまで眠ってはいけないヤバい夜

そしてこの干支は年単位だけではなく日ごとにも巡るのです。こちらは60日で一巡しながら繰り返されています。「庚申(こうしん・かのえさる)」も、「乙未」」と同じく干支の一つ。「庚申の日」とはつまり庚申の輪番の日のことです。
この日の夜に「庚申講」「庚申待ち」と称して夜通しの宴会をする風習があったのです。ということはおめでたい日なのでしょうか。むしろその逆で「庚申」は不吉な日だとされていました。
十干も十二支も、中国の五行思想(万象は火・土・木・水・金の五種類に分けられ、さらにそれぞれが陰と陽の二種類があるとする世界観)が根底にあり、「庚」は五行の金気の陽、「申」も金気の陽であり、金と金とがぶつかり、かつ陽の日は万象は活動的になるため、人々が殺気立ち、刃傷沙汰(金気の災い)がおきやすいと考えられたのです。
そしてこの庚申の日には、もうひとつまずいことがあるとされていました。
庚申の日の夜、人が眠りに就くと体内に住んでいる三尸(さんし)と呼ばれる虫が身体から抜け出し、その人の悪い行いを天帝(または閻魔大王、道教では司命道人)に報告し寿命を縮める、と信じられていたのです。
小さな過ちならば三日、大きい過ちではなんと300日寿命を縮められてしまうのです。
ちなみに人間は天から120歳の天寿を授かっていて、誰でも本来120歳生きられるんだそう。このもともと与えられた120年から毎回の庚申の日の三尸の告げ口で寿命が削られていってしまう、ということですね。そりゃたまらん、ということで、庚申の夜はこの三尸が抜け出して告げ口に行かぬよう徹夜する勤行=守庚申が生じました。
平安時代には貴族や僧侶のみが守庚申を行なっていました。不眠ですごろくをしたり詩歌管弦に興じてすごしていたようで、「枕草子」や「源氏物語」にも守庚申の記述が出てきます。清少納言や紫式部は、現代のパーティーピーポーの元祖かもしれませんね。
一番鶏が鳴く(朝になる)と守庚申は明けます。申(猿)の次は酉(鶏)ですから、偶然なのかこじつけなのか、うまくできているものです。
東照宮のあの超有名スター彫刻も庚申信仰に関係あり!

あの日光の人気者も元はといえば…
そしてこれらの仏神の像の下には小さく三匹の猿があの日光東照宮のもっとも有名な彫刻「見ざる・言わざる・聞かざる」のポーズを取って彫り込まれています。人間の寿命をつかさどるのは北斗七星(妙見菩薩)といわれていました。そこで、三尸が報告に行く北斗七星と天帝が結びつきました。
さらに北斗七星を祀ったのが山王神社。山王様の眷属・使者は猿。そして三尸に対応させて、三匹の猿が戒めの姿として彫られるようになりました。もちろん日光東照宮の「見ざる・言わざる・聞かざる」の彫刻も、庚申信仰が民間、権力層を問わずいかに普及したものだったかをあらわしています。
猿と庚申信仰が結びつくと、神道の猿田彦神ともさらに結びつき、神社では猿田彦が庚申さまとしてあがめられるようになりました。
こうして庚申さまは日本中津々浦々、各地の村の「講」として定着し、人々は60日の一度巡ってくるこの日を夜通し酒盛りする宴会の夜として楽しむようになったのです。といっても、なんでもありの無礼「講」ではありません。
まず、最初に入浴して身を浄めたあと祭神を拝まねばなりません。夜業や結髪なども禁止で、食べ物も肉類やニラ、ネギ等の香味野菜を避けねばならない地域もあったり、また、金属類を身につけることも禁止です。
そして、夫婦の同衾、つまり子供を作ることも大きな禁忌とされていました。この日に授かった子供は、後々泥棒になるとか、体が不自由になるとかいわれていたためです。体のほうは由来はわかりませんが、泥棒になるというのは、先述した刃傷沙汰とか、あるいは金属つまりお金に執着する人間になる、という俗信からでしょう。
こうして庚申講を勤め続け、それが18回を数えると(約三年)、年季明けに先祖供養をかねて講集団で庚申塔を建てたので、各地にたくさんのさまざまな庚申塔が残され、近世の貴重な民俗学的資料となっています。
「講」という名のクラブ活動

たとえば修験者が広めて全国各地の山に参る登山サークルのような出羽三山講や富士講、有名寺社に参拝する旅行サークルとしては伊勢講、金比羅講、成田講など、女子会サークルの二十三夜講、女人講、研究サークルの神農講、念仏講などなど。
また、講は会費を徴収して一種の村の互助会としても機能していました。中には無尽講(むじんこう)、頼母子講(たのもしこう)などのように、後に金融機関並みの資金力を有する互助会に発展するものもあったようです。
これらの講もそれぞれに参拝記念や年季明けに石碑を建てたので、墓地や寺社の片隅、古い街道の道沿いなどにさまざまな講の石碑が残っています。近所のそうした石碑をさがしてみるのも面白いのではないでしょうか。思いがけない地元の歴史を知ることができたり、もしかしたら、私たちの住む町のすぐ近所でも、今も「庚申講」が行なわれていたりするかもしれませんよ。
ところで干支といえば来年は申年。幸いなことにかどうかはわかりませんが、庚申ではなく丙申(ひのえさる)年です。
五行思想では丙が火、申が金で「火剋金」となり、火によって金が溶かされる意味となります。となるともしかしたら経済的にはあまりいい年回りではないのかも。でも、丙も申も、勢いよく生い茂る意もあります。大きな発展や変革のある年になる、とも言えるようです。