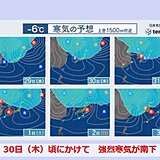「センス・オブ・ワンダー」という感性。レイチェル・カーソンからの贈りもの

4月14日は、その著書『沈黙の春』で知られるレイチェル・カーソンの命日です。1907年にアメリカのペンシルベニア州で生まれたレイチェルは、海洋学者として公職につき、ベストセラー作家としても活躍しました。すべての子どもが生まれながらに持つ感性「センス・オブ・ワンダー」、それを失わない大人になるには。美しい詩情あふれる文章で綴られた、レイチェルの最後のメッセージをご紹介します。
「環境問題」をはじめて提示した『沈黙の春』

この晩年の歴史的著作は、友人からの一通の手紙がきっかけとなり誕生しました。当時のアメリカでは化学物質の開発が進み、その危険性が検証されないまま大量に実用化されていました。そのような状況のなかで、役所によって殺虫剤が空中散布された結果、友人の庭にやってきた小鳥が次々と死んでしまうという事件が起こります。鳥たちのさえずりが聞かれなくなった「沈黙の春」…。
レイチェルは、このような事態を4年の歳月をかけて検証し、環境の汚染と破壊の実態を告発しました。『沈黙の春』は、発表と同時にアメリカ社会に大きな反響を巻き起こし、やがて世界中で農薬の使用を制限する法律の制定が促されることになるのです。
レイチェルの最後のメッセージ『センス・オブ・ワンダー』

本の扉には、このような短いコメントが記されています。
「レイチェル・カーソンはこの『センス・オブ・ワンダー』をさらにふくらませたいと考えていた。しかし、それを成し遂げる前に、彼女の生命の灯は燃え尽きてしまった。生前、彼女がねがっていたように、この本をロジャーにおくる」
ロジャーはレイチェルの姪の息子で、『センス・オブ・ワンダー』はロジャーとレイチェルがいっしょに海辺や森のなかを探検し、星空や夜の海を眺めたかけがえのない経験をもとに書かれた作品です。
「子どもたちの世界は、いつも生き生きとして新鮮で美しく、驚きと感激にみちあふれています。残念なことに、わたしたちの多くは大人になるまえに澄みきった洞察力や、美しいもの、畏敬すべきものへの直感力をにぶらせ、あるときはまったく失ってしまいます。もしもわたしが、すべての子どもの成長を見守る善良な妖精に話しかける力をもっているとしたら、世界中の子どもに、生涯消えることのない“センス・オブ・ワンダー = 神秘さや不思議さに目をみはる感性”を授けてほしいとたのむでしょう。」
「知る」ことは「感じる」ことの半分も重要ではない

「子どもと一緒に自然を探検することは、まわりにあるすべてのものに対するあなた自身の感受性にみがきをかけるということです。それは、しばらくつかっていなかった感覚の回路をひらくこと、つまり、あなたの目、耳、鼻、指先のつかいかたをもう一度学び直すことなのです。」と、レイチェルは記しています。
子どもに驚異の目をみはらせることは、大人の自分に対しても同じことがいえそうです。大人になるにつれ、はじめて見るものや経験することが減っていきます。そして、どんどん驚きや感動といった感性を手離してしまうのかもしれません。
「子どもたちが出会う事実のひとつひとつが種子だとしたらさまざまな情緒やゆたかな感受性は、この種子をはぐくむ肥沃な土壌です。幼い子ども時代はこの土を耕すときです。」
「地球の美しさについて深く思いをめぐらせる人は、生命の終わりの瞬間まで、生き生きとした精神力をたもちつづけることができるでしょう。」
「知る」ことは「感じる」ことの半分も重要ではない。自然を通して何かに出会い、それに対して強く感じるとき、その先に確固たる知識や知恵が生まれ、生き生きとした精神力が生まれる。レイチェルからの力強いメッセージが、かつて子どもだったすべての大人に贈られているようです。
レイチェル・カーソン/上遠恵子・訳『センス・オブ・ワンダー』新潮社 1997