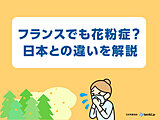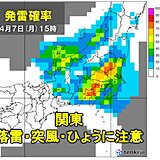「紅葉狩り」。何かを狩るわけではないのに、なぜ“狩り”?

「紅葉狩り」「紅葉見」「観楓会」。紅葉観賞のよび方いろいろ

一般的には「紅葉狩り」といわれていますね。春に桜の花を楽しむように、秋は落葉樹の葉が落ちる前の、色とりどりの葉を眺めて楽しみます。紅葉狩りのほかに、「紅葉見(もみじみ)」という言い方もあります。意味としては紅葉狩りと同じで、どちらも日本の秋の風物詩です。
北海道では紅葉見物のことを「観楓会(かんぷうかい)」とよんだりします。漢字が表すとおり、楓などの紅葉を観る集いのことですが、花見のように紅葉した木の下で宴会を催すわけではなく、会社などで温泉一泊旅行などの懇親会といった意味合いのほうが強いかもしれません。
ここで疑問なのは、桜を見るのが「花見」なのに、紅葉を見るのはなぜ「紅葉狩り」とよぶのか、ということです。「紅葉見」というよび方もありますが、よく言われるのは「紅葉狩り」です。何かを「狩る」わけではないのに、紅葉狩り。そこには何か歴史的な意味が隠されていそうです。
りんご狩り、ぶどう狩り、きのこ狩り。植物の採集にも「狩り」を使う

果物だと「りんご狩り」「ぶどう狩り」「いちご狩り」「さくらんぼ狩り」をはじめ、「プルーン狩り」「なし狩り」「みかん狩り」など、主に果樹園で果物を採取するときに使われます。また、山野では「きのこ狩り」「山菜狩り」「ふき狩り」など、海岸線では「潮干狩り」「あさり狩り」などが行われます。これらはいわゆる狩猟ではありませんが、植物や魚介類をとるので「狩り」が使われます。
この「狩り」という言葉は、実際に何かをとるのではなく、「紅葉狩り」や「桜狩り」のように、季節の花や草木の美しさを観賞するときにも使われます。したがって、「ほたる狩り」は蛍を実際に捕らえるのではなく、蛍を観賞して楽しむことを表します。
でも、美しいものを観賞するときに、なぜ「狩り」という言葉が使われるのでしょう。その語源は平安時代までさかのぼります。
平安貴族が歩くことは下品。でも「狩り」だったら歩いて山に行ける

さらに、移動するには牛車や馬に乗らなければならず、自分の足で歩くことは下品だと考えられていました。とはいえ、山に出かけて紅葉を楽しみたい。そこで、「狩り」という名目で山に行けば、たとえ山の中を自分の足で歩いたとしても、貴族としての体裁が保たれます。こうして、紅葉を見にいくことを「紅葉狩り」とよぶようになりました。
参考
国立国会図書館「レファレンス協同データベース」:ホタル狩りはなぜ「狩り」というのか
NHK「チコちゃんに叱られる!」:紅葉狩りはなんで狩りっていうの?