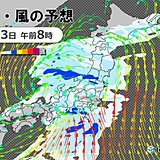≪紅花栄≫いにしえより衣や乙女の唇を“くれなゐ”に染める「べにばな」歴史ものがたり

紅花の開花時期は梅雨のころ~7月中旬と少し先のようですが、アザミにも似た橙黄色の花の花びらは、古代より染料や生薬として貴重な存在でした。いにしえの貴人たちの衣を染め、女性の頬やくちびるを美しく彩ってきた「紅花」について、その歴史を少し追ってみましょう。
古代エジプトではミイラの屍衣、万葉時代には優美な女性がまとう衣を染めた「紅花(べにばな)」
古代より染料や虫よけにも使われたという歴史をたどってみると、なんと、遥か紀元前2500年前のエジプトへ。碑文に紅花のことが記され、紅花で染めた布でミイラを包み屍衣にしていたといいます。
中国への伝来は、紀元前2世紀頃。そして日本へは、推古天皇の御世・600年頃、高麗より伝わったという説が有力だとか。万葉集で詠まれている「紅(くれなゐ)」という言葉は、この紅花で染めた衣をさしていることが多いようです。
黒牛潟潮干(くろうしがたしほひ)の浦を紅(くれなゐ)の
玉裳(たまも)裾引き行くは誰(た)が妻 ~柿本人麻呂~
これは、赤い衣裳の裾を引くしとやかな女官の姿を詠んだもの。このほか紅の衣、紅の裾、紅の薄染衣、紅の赤裳など、「くれなゐ」という語がさまざまな歌に詠み込まれ、紅の衣をまとった優美な女性の姿を彷彿とさせます。
別名は、源氏物語でもおなじみ「末摘花(すゑつむはな)」。そして「呉藍(くれのあい)」

染め色の薄いものから濃いものまで、薄紅(うすくれなゐ)、濃紅(こきくれなゐ)と呼び分け、濃い紅は舶来ものを表した唐や韓などをつけ「唐紅、韓紅(共にからくれない)」とも呼ばれました。
紅花から濃い紅を染めるには、大量の花びらと複雑な工程が必要であったことから、濃い紅は禁色として着用が制限されていました。ごく薄くピンク色に染めた「一斤染(いっこんぞめ)」は、位のあまり高くない役人にも着用が許された、聴し色(ゆるしいろ)だったとのことです。
また紅花には、茎の先端に着いた花を摘むことから、「末摘花(すゑつむはな)」という別名もあります。紫式部が綴った源氏物語に登場する女性は、象のように長い鼻を持ち、その先が赤いことから「末摘花」と呼ばれてましたね。そんな滑稽だけれども、少し切ない物語のほか、秘めた思いを表す言葉としても使われた「紅」や「末摘花」。
人知れず思へば苦し紅(くれなゐ)の
末摘花(すゑつむはな)の色にいでなむ
~古今和歌集/よみ人しらず~
いにしえの歌集を紐解けば、人が人を恋い慕う熱い思いが、時空を超え伝わってくる歌にたくさん出会えます。
口紅が町娘たちにも普及した江戸時代。今も残る玉虫色に光る華やかな「紅(べに)」

そのころ最上川流域は紅花の一大産地となり、山形の紅花は京都や大阪で大変重宝されました。
紅花を用い丹精込めて仕上げた紅は、意外にも、玉虫色の輝きを放つのが特徴。おちょこやお皿、お碗、貝殻などの内側に刷(は)かれた状態で市販され、娘たちのあこがれを集めました。
この玉虫色の紅を下唇にたっぷり重ね塗りし、緑色(笹色)にする化粧法「笹紅(ささべに)」が文化文政の一時期大流行。
その際、高価な玉虫色の紅をふんだんに使うことが叶わない庶民の娘たちは、ユニークな裏技をひと工夫。なんと唇にまず墨をのせ、その上に紅を重ねることで、紅の下から浮かび上がる玉虫色に近い輝きを作り出したとのこと。今も昔も美を求める乙女心は変わらないというエピソードです。
古来神聖な色とされた赤のなかでも、「ぬくもりの薬」と呼ばれ、血の巡りを良くするとされる紅の赤は、女性の通過儀礼にも使われてきた特別な色。
七五三や十三参り、お嫁入りで白無垢をまとうとき、そっと唇に紅をひとさしするのも、幸せを祈りことほぐ心の表れです。
おちょこ一つ分の紅を作るのに必要な花は、約1000輪。そんなおびただしい数の紅花の花びらから生まれた希少な紅が、特別な日を迎えた女性のくちびるをほんのりと染める様子は、見るものの心をうばう華やかさ。ゆくすえまでも守ってくれる聖なる色が、命そのものを美しく輝かせてくれるかのようです。
※参考/「色の名前」ネイチャー・プロ編集部(角川書店)
万葉植物事典(北隆館)