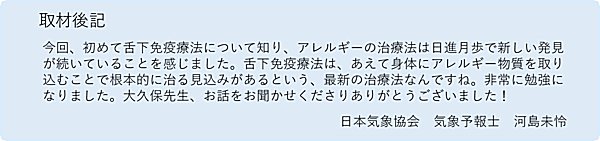花粉対策は早めが肝心!今からできる花粉症対策PR

今年の花粉飛散予測
今夏の気象条件などに基づく予測では、2016年春の花粉総飛散数(スギ及びヒノキ、北海道はシラカバ)は、東北地方で例年並みか多く、その他の地域では例年並みか少ない見込みです。ただし、前シーズンの2015年春は飛散数が例年より少ない地域が多かったため、前年と比較すると同程度か多くなることが予測されている地域もあります。
また、シーズンを通じた総飛散数が少なくても、気象条件の良い日などに大量の花粉が一斉に飛散する場合もありますので、花粉シーズンに向けて、油断せずに対策をとっていくことがおすすめです。
私もスギ花粉症なので、今からとても憂鬱です。今の時期からできるスギ花粉症対策を、日本医科大学の大久保教授にお伺いしてきました。

耳鼻咽喉科学講座 主任教授
大学院医学研究室頭頸部・感覚器科学 教授
附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科 部長
医学博士 大久保公裕 先生
一般財団法人 日本気象協会
気象予報士 河島未怜
花粉シーズン前からできるスギ花粉症対策
大久保先生:スギ花粉症の患者さんは年々増加しています。その理由には、スギ花粉の増加があります。スギ花粉は、樹齢が20年以上の成木で作られます。樹齢30年以上になると、特に活発にスギ花粉が作られます。現在、戦後の国策として植林されたスギの大半が、樹齢30~40年となっており、活発に花粉を産生する時期を迎えています。そして今後しばらくは、樹齢30年以上のスギが増加傾向にあり、飛散するスギ花粉も増加する見込みです。
河島:今後さらにスギ花粉が増加傾向にあるとはショックです…。次の花粉シーズンも不安なのですが、シーズン前からできる対策にはどのようなものがあるのでしょうか?
・食生活による対策
河島:花粉症対策として、私は『甜茶』を飲むようにしています。飲むようになってから、花粉シーズンも以前より辛くない気がするのですが、対策としていかがでしょうか。
大久保先生:花粉症への効果が示されている食品もありますね。甜茶等に含まれる抗酸化作用のある『ポリフェノール』もその一つです。ポリフェノールは、アレルギー反応を引き起こすヒスタミンの生成を抑える効果もあります。他に、玉ねぎの皮に含まれる『ケルセチン』もポリフェノールの一種で、アレルギー体質の改善に効果があるとされています。
河島:玉ねぎは身近な食材ですね!しかし、玉ねぎの皮はむいてしまうことが多いと思いますが、どうすれば普段の食事で『ケルセチン』を摂ることができますか?
大久保先生:玉ねぎの皮ごとくたくたに煮て、カレーなどにするのもいいですね。
河島:そうなんですね。ポリフェノールには抗酸化作用もあるので、肌にも良さそうですし、女性には嬉しいことばかりですね!
大久保先生:ポリフェノールの他、アレルギーの改善につながるものとして、ヨーグルトなどに含まれる『乳酸菌』があります。『乳酸菌』は体内の免疫バランスを整えてくれる作用があると言われています。
河島:ヨーグルトもいいんですね。私はヨーグルトが大好きなので、これなら毎日続けられそうです!

大久保先生:食生活だけでなく、適度な運動をして汗をかくなど、毎日の生活習慣を整えることによっても、花粉症の症状の緩和につながることがあります。
河島:どのようなメカニズムなのでしょうか?
大久保先生:自律神経のはたらきを整えることに意味があります。自律神経には、緊張時に働く交感神経とリラックス時に働く副交感神経がありますが、適度な運動などで交感神経が優位な状態を作るようにすると、花粉症の症状が出にくくなります。また、生活リズムにメリハリをつけることで、副交感神経だけでなく、交感神経を使う習慣がつきます。
河島:スギ花粉シーズンに向けて、メリハリのある生活で自律神経のはたらきを整えていくことも大切なんですね。

大久保先生:また、薬による初期治療を選択することもできます。花粉が飛び始める1~2週間前に医療機関を受診し、抗アレルギー薬や抗ヒスタミン薬などを服用することで、発症してから薬を服用して対処するより、症状を軽減させることができます。
河島:私も長年スギ花粉症に苦しんでいるので、シーズン前に医療機関にかかるようにしています。他に、レーザーによる治療もあると聞いたことがあるのですが…
大久保先生:はい。日帰りの手術で、鼻の粘膜にレーザーを照射して症状を軽減させる方法があります。ただ、粘膜は数ヵ月~2年で再生するので長期的な効果は期待できません。最近では、『舌下免疫療法』という治療法が注目されています。スギ花粉症の症状を和らげるだけではなく、スギ花粉症を治すことも期待される治療法です。
河島:ちなみに『舌下免疫療法』とはどのような治療なんでしょうか?
大久保先生:舌下免疫療法は、スギ花粉に反応する体質そのものを改善する「根本的治療」です。アレルギーの原因物質であるスギ花粉を原料としたエキスを舌下に毎日投与して、アレルギー反応を弱めていく治療法で、継続的に行うことがポイントです。
河島:アレルギーの原因物質であるスギ花粉のエキスを舌下に投与することが、治療になるとは興味深いですね。
大久保先生:そもそもアレルギーとは、本来ならば体を守るための免疫が過剰になり、自分自身を攻撃することで起こる病気です。アレルギーで起こっている問題である免疫系の攻撃力に働きかけて、過剰にならないようにするという治療法が舌下免疫療法です。
河島:以前にも注射で行うスギ花粉症の治療法を耳にしたことがありますが…。
大久保先生:はい、これまでも皮下に注射でスギ花粉のエキスを投与する皮下免疫療法と呼ばれる治療法はありましたが、頻繁に通院が必要で、注射のため痛みも伴います。それに比べて舌下免疫療法は、自宅で行えますので、皮下免疫療法より通院回数が少なく、痛みもないのが特徴です。
河島:どのくらい治療を続ける必要がありますか?
大久保先生:1日1回、自宅で舌下に投与し、少なくとも2年間は続ける必要があります。治療を始める前に医師の診断を受け、その後も定期的な通院が必要です。
毎日、患者さんご自身が投与する治療法ですので、毎日きちんと続けられるという方が向いています。最終的にはスギ花粉症を治すことを目指し、3~5年の治療が推奨されています。
河島:年単位での治療だと、根気が必要ですね…。
大久保先生:そうですね。ただし、そこまで構えずに、「顔を洗う」、「歯磨きをする」のと同じように、毎日の習慣の1つに入れるように考えると気が楽になるかもしれませんね。
また、徐々に体質を変えていく治療法ですが、1シーズン目から症状が和らぐことを実感される患者さんもいらっしゃいます。厚生労働省研究班の調査では、治療を行った患者さんに今年の花粉飛散時期の症状を尋ねたところ、約80%の患者さんが例年と比べて症状が改善したとの結果を発表しています。この治療法は、スギ花粉が飛散する前に始めることが必要です。
河島:では、いまから始めれば、来春に間に合うこともあるということですか?でも、まだ症状の無いこの時期から、病院にいくとなると大変かなと思ってしまいますね。
大久保先生:そうですね。しかし、今から始めることで、スギ花粉の飛散量にもよりますが、いつものシーズンより症状が軽減することが期待できますし、10月からは月に1回程度の受診で治療できるようにもなりました。
河島:この治療は誰でも受けられるのでしょうか? 例えば、私でも受けられるのでしょうか?
大久保先生:現在は、12歳以上のスギ花粉症の方であれば、基本的に受けることができます。ただし、患者さんによってはこの治療法に適していない方もいます。まずは治療を始める前に、医師による診断が必要です。
治療の開始は、スギ花粉シーズン前、例えば関東では年内であれば可能です。
河島:なるほど。早速、私も治療を受けられるか病院に行ってみたいと思います。
大久保先生:舌下免疫療法について相談できる医療機関を検索できる、WEBページもありますので、興味があれば調べて相談してみるのもよいのではないでしょうか。
河島:スギ花粉症のためにいままで飲んでいたお薬を減らしたい方や、副作用がつらい方、毎年の症状に悩みたくない方におすすめの治療法ですね。