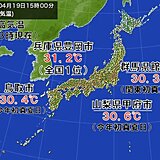文月は、神話の火の神と関わりあり?和風月名「文月」考

旧暦文月は盛夏の頃。熱帯が故郷の稲は、真夏の熱気の中で出穂します
旧暦は太陰太陽暦で設定されており、現代の暦でいう文月は7月下旬から9月上旬頃の期間で年により移動しました。つまり、おおよそ学校が夏休みの期間中と重なる、一年でもっとも気温が高く、むしむしする「日本の夏」の時期といえるでしょう。和風月名の由来はほとんど明らかではなく、文月も他の月と同様ですが、文月の名称には他の月にはない、こじれた、しかし実に面白い問題があります。
月の不可解。なぜこの月のみ音読みなのか?

火の神・軻遇突智(かぐつち)の血潮がかかった草木石礫(いしむら)には火の霊が内包されることに
文月の意味についての諸説は、以下の通りです。
(1)文月に行われる七夕の行事にあやかり、『四民月令』(崔寔 後漢時代)に「七月七日曝二經書及衣裳一不蠹」とあり、七夕の日に書籍や着物を広げて空気にさらし、虫干しをするならわしがあり、日本でもこの日、文書を広げて虫干しをすることから「文被月(ふみひろげづき、ふみひらきづき)」となった、というもの。曝書の習慣から文月となった、という説を採っているのは『奥義抄』『下学集』『日本歳時記』等多くあり、多数派の説になっています。
(2)稲の穂が膨らみ始める穂含(ほふくみ)月から転じたとする説。『古今要覽稿』(屋代弘賢 1821~1842年)で「ふみづきの名は、ふくみ月の義にとるかたしかるべし、此月稻穗を含めり」とし、賀茂眞淵も「穂含み月」の意であると続けています。跡部良顕や谷川士清は、「穂含み」ではなく「穂見(ほみ)」つまり稲穂が葉の間から見え始める月、としていますが、ほぼ同じ説です。
(1)説に関しては、真偽はともかくとして、「和風月名は日本古来の独自の月名」という仮定(前提)を無視してしまっています。七夕行事は中国渡来であり、日本の伝統ではない、ということから、この説に対して指摘が相次いでおり、多数派説であるにも関わらず、根拠の弱い仮説どまりになっています。そしてそれ以上に、「文」を「ふ/ふみ」と音読しているという時点で、仮説の前提を失っています。「ふみ」という言葉が何となく大和言葉と思われてしまっているせいでしょうか。
ですから、理屈からして正しいのは(2)なのですが、現代ならここからもう少し踏み込むことができます。なぜなら私たちは、水田稲作が日本列島の始原からおこなわれていたものではなく、和風月名を水田稲作に強引に結びつけるのは無理があることを知っているからです。稲作以前の日本人がどう生き、何を感じ、何を大切にしていたかをより深く考えてみましょう。
古代人は万物に火の霊が宿ると考えていた

炎とは熱源から立ち上る火の穂(ほのほ)
二十四節気の「芒種」も、イネ科の草が穂をつける頃という意味です。長い狩猟採集中心の生活の中で培われてきた感覚からすると、より広く自然の変化を感じ取っていたはずです。
稲穂の「穂(ほ)」とは、高く飛びぬけたもの、形をあらわしますが、「ほ」という音は古語では「火」をもあらわします。炎(ほのお)は「火(ほ)の穂」です。火は本来熱源そのものを意味し、炎はその熱源からめらめらとたちあがる、いわゆる「火」のことでした。
日本書紀・神代上・第五段・一書の第八には、以下のような記述があります。
(書八)
一書に曰はく、伊弉諾尊(いざなぎのみこと)、軻遇突智命(かぐつちのみこと)を斬りて、五段(いつきだ)に為す。此各五(これおのおのいつつ)の山祇(やまつみ)と化成(な)る。一は首(かしら)、大山祇(おおやまつみ)と化為(な)る。二は身中(むくろ)、中山祇(なかやまつみ)と化為る。三は手、麓山祇(はやまつみ)と化為る。四は腰、正勝山祇(まさかやまつみ)と化為る。五は足、しぎ山祇と化為る。是の時に、斬る血激越(そそ)きて、石礫(いしむら)・樹草に染(そま)る。此(これ)草木・沙石(いさご)の自づからに火を含む縁(ことのもと)なり。
軻遇突智命は、一書の第三では火産霊(ほむすび)とも記述される火の神で、この神の出産で母神伊契冉(いざなみ)は火傷を負い、神去ってしまうという神話は有名ですね。
妻を失った伊弉諾は怒り、軻遇突智をばらばらに(一書第八では五つに)切り裂いてしまいます。すると身体のパーツがそれぞれ別個の神となると同時に、火の神の飛び散った血が草木や石に染みこんで、それ以降、草や木はその内部に火(火気)を含むようになった、と語られます。この神話は、火打石や火起こし棒から火が生じる不思議を、自然の事物に火の神が分霊されているからだ、と考えた古代人の感覚をよくあらわしています。
そして、自然の草木の内なる火が作用して、赤や黄、褐色に実る果実や穀果をふくらませ、炎=火の穂のように草の間から穂が燃え立つのだと考えたのです。
ぎらぎらと太陽が照りつけ、焚き火にあぶられるような真夏。自然界が「火・産み」「火・膨らむ」季節であることを、「ふみ月」と呼んだのではなかったでしょうか。あるいはもっとシンプルに、火霊の作用が強まり気温があがる季節を、「火、充(みつる)月」で「ふみ月」と名づけたのかもしれません。上代(奈良時代から以前の時代)において、は行はp音もしくはf音で発音されていたと推測されています。となると、文月の「ふ」は「ふゅ/fyu」、さらに古くは「ぷ/pu」と発音されていたことになります。f音やp音は、柔らかいh音よりも強く響く子音ですから、火=pi、po/fi、foから、日本語の変化と共にいつしか母音が抜け落ちてp、fとなり、これがhu→「ふ」と変化したことも想像できます。
半夏生。語源となる夏安居の美しい精神とは

稲の穂もまた、稲に分与された火の力が炎のように燃え立つように見えます
七十二候で雑節と字面が同じになるのはこの「半夏生」以外ありませんから、何かとややこしいのですが、その分さまざまな媒体で説明されることが多く、ご存知の方も多いことでしょう。
「半夏」という植物が生じる頃、という意味のハンゲ。ドクダミ科の水沢植物・片白草(カタシログサ)が別名「半化粧」といわれ、これが「半夏生」に転じたとされます。本来は、漢方生薬で「半夏」といわれる畑の雑草でサトイモ科のカラスビシャクのことを意味するというのも、多くで語られています。「蛇みたいで気持ち悪い」と言われがちなカラスビシャクですが、筆者は、カラスが足であの仏炎苞(ぶつえんほう)をつかんで水をすくって飲む様子を想像して、かわいい植物だなあ、と思うのですが…。
雑節の半夏生について、現在ではその日取りを「太陽黄径が100°となったとき」と、注釈もなくあっさり説明されているのを見かけますが、太陽黄径と言ってピンと来る人がどれだけいるのだろう、と常々疑問でしたので、太陽黄径について説明しようと思います。
ご存知の通り、地球は太陽の周りを一年かけて周っていて(公転)、地球自体の自転軸はその公転軌道の正対面(垂直面)に対して、23.4°傾いています。赤道(地球の自転軸に垂直で、かつ地球の中心・重心と切断面が交わる地球表面を一周する直線)を、宇宙の天球まで拡大したものが天の赤道、これに対して黄道(地球から見た太陽の天球軌道)は、地球の自転軸の公転軌道からの傾き分、傾いています(黄道傾斜角)。天の赤道と黄道という二つの大きな円環(リング)は、二箇所のみで交わっていますが、この二箇所が春分点と秋分点です。黄径とは、このうち春分点を0°として、黄道を360°に分割して、一年のうちの太陽の位置をあらわしたものです。春分点が0°ですから、対角にある秋分点は180°になります。夏至は直角の90°、冬至は270°となります。半夏生の黄径100°とは、夏至から10°すすんだ点、ということになりますね。
「半夏」とは、もともとは仏教の故郷、インドの修行僧に由来します。6月から10月、インドは雨期で、修行僧は托鉢に出ることでこの時期に多く這い出てくる虫や両生類などの小動物や、草木の新芽を踏み殺してしまうことを厭い、托鉢などの修行を停止し、僧房に篭って修行に専念することを倣いとし、これを「安居」と言いました。
中国から日本へと伝播した北伝仏教でも、安居は踏襲されましたが、気候にあわせて期間が変更されました。旧暦4月16日からの90日間を夏安居と定め、安居の初日を結夏(けつげ)、最終日を解夏(げげ)、中間の折り返し日を半夏(はんげ)と言いました。旧暦で5月の半ば、新暦(太陽暦)でいえば6月中旬から7月下旬となり、今の7月初旬はちょうど真ん中にあたり、凡そ「半夏」の時期、ということになるわけです。
農事の目安の雑節としても、この時期は入梅からほぼ20日にあたり、約40日続く梅雨の折り返しに当たるため、「半夏」の「半」と重なります。

カラスビシャク(半夏)。カラスがこの柄杓で水を飲む姿を想像してほっこりしませんか?
(参考・参照)
日本書紀 日本古典文学体系 岩波書店