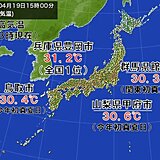林下に花開く胡蝶の化身「シャガ」。その不思議な名前の由来とは?

舞い飛ぶ蝶のような姿から本来は「胡蝶花」と呼ばれるシャガ
中世に渡来した帰化植物シャガ。風土に溶け込んでいつしか「日本のアイリス」に

京都府綾部市の幻想的なシャガの大群落
4~5月ごろ、アヤメの仲間では最も早く、直径5センチほどの一日花を数多くつけます。花弁全体は純白もしくは淡紫青色で、林下で青白く浮き上がって見えます。多くのアヤメ類の特徴である下に垂れ下がった外花被片は、ハナショウブやアヤメと比べると小さめで斜め下に緩やかに垂れ下がり、この外花被片表面にオレンジ色の斑と、とさか状の突起があり、それを取り囲むように青紫の斑が入ります。
また、外花被片の縁と、上に向かって立ち上がった白い花柱枝は細裂し、レース飾りのスカートのように見える、かわいらしいデザイン。
低地・人里近くの湿った森林の林床に普通に見られますが、染色体は三倍体(2n=54)で、不稔性で種子を作りません。そのかわり、横に長く這う地下茎から細いストロン(匍匐枝)を出しその先に新芽を作って旺盛に増えていきます。このためヒガンバナなどと同様に、しばしば一面の大群落を作ります。
京都府綾部市の大群落は特に見事で有名です。沖縄、北海道を除く日本各地に自生し、学名もIris japonica=「日本のアイリス」とまで名づけられているのですが、在来種ではなく中国からの帰化植物です。
渡来時期は多くの場合、史前帰化とされているのですが、そのわりには万葉集にも枕草子にも源氏物語にも登場せず、文献上では『山科家礼記』(応永19年/1412年~延徳4年/1492年)の延徳3(1491)年に「しやくわ」として記載されているものが最古となり、江戸時代ごろから急激に言及されはじめたため、実際のところは室町時代ごろに渡来したものでしょう。
原産地の中国では、このシャガを「胡蝶花」と呼び、日本にもこの名前は移入されて、表記もされていたのですが、いつの頃からか胡蝶花ではなく、「シャガ」というあまりこの花の印象にふさわしくない不思議な名前に変わってしまいました。この呼び名の背景には、複雑な経緯があります。
「射干」とは、尸林をさまよう恐ろしい魔物のことだった

もとはこの日輪のようなヒオウギを「射干(シャガ)」と呼びました
ヒオウギ(檜扇 Iris domestica)は、本州以南に自生するアヤメ科アヤメ属の多年草の在来種。草丈は50~120センチ、生育地は高原や低地の日当たりの良い湿原。平たい板を並べて束ねた王朝貴族の檜扇のように、板状の葉が扇状に広がる特徴的な形状から「ヒオウギ」と名づけられました。
夏ごろに咲く花は六枚の花被片が放射状に開き、アヤメの他の多くの仲間のように垂れ下がる花被はありません。花被片全体が鮮やかなオレンジで、赤い斑が全体に入ります。花が枯れた後の実は漆黒でつやつやとし、これをぬば玉(射干玉、烏羽玉、野干玉、夜干玉)と呼びます。和歌では「夜」「黒」にかかる枕詞として有名ですよね。
「射干」という妙な名前は、サンスクリット語の「シュリガーラ」(शृगाल śṛgāla)が「野干」「射干」「夜干」と漢訳されたものといわれています。ヒオウギの実の「ぬば玉」が「射干玉」「野干玉」という漢字が当てられるのもこのためです。
シュリガーラとは尸林(しりん 死者を火葬した後、亡骸を放置する特定の森)に棲み、死体を貪る魔獣で、一説ではジャッカルのことともいわれていますが、インドの殺戮と戦争の黒い女神カーリーの眷属で尸林をさまよい死体を食らう夜叉ダーキニーとも同一視されます。
ダーキニーは後に仏教の守護眷属・荼枳尼天(だきにてん)となり、日本では稲荷神となり、狐に乗った女神(天狗)、あるいは狐そのものが「野干」と呼ばれるようにもなりました。キツネのオレンジ色に近い被毛はヒオウギの花色とも通じます。黒いぬば玉と朱色の花は、闇と血に結びつく夜叉の花のイメージにぴったりです。
またそれとは別に、射干という言葉は、中国古代の地理書『山海経』に記された炎帝神農の夫人・義和の十人の息子たち=十個の太陽神話を想起させます。
十個の太陽は干支の十干であり、空に同時に十個の太陽が出たために九つの太陽は射落とされ、射落とされた太陽はカラスとなって地に落ちたといわれます。この射日神話は、日本では「オビシャ」となって民間信仰行事として伝わりますし、また太陽にヤタガラスが棲むという信仰も有名です。
ヒオウギの花は日輪のようにも、また矢の的のようにも見えますし、ぬば玉の実は「烏羽玉」、つまりカラスにも喩えられるわけで、不思議な符合があるものだと思わずにはいられません。
これほどヒオウギと射干という名には強いイメージの結びつきがあるのです。これが、清楚な青白い日陰の花にすり変わるなど、容易ならざることではないでしょうか。なぜそうなったのか、筋道たてて考えてみましょう。
カラスオウギ、ヒオウギアヤメ、イチハツ…アヤメ族の幻惑が名前を次々に転写させた?

イチハツ。シャガとともに「Crested iris(とさかのあるアイリス)」のグループ
北アメリカからアジアの広域の亜寒帯、温帯の湿原に分布するヒオウギアヤメ(檜扇菖蒲 Iris setosa)です。日本では本州の高山や寒冷地、北海道に自生し、7~8月ごろ咲く花は内花被片が小さいという特徴以外はアヤメによく似ていますが、葉はヒオウギによく似た檜扇形になるため、"ひおうぎ”の名がついています。
さらに、中国から「鳶尾」と称するアヤメの一種が中世室町時代(文献初出1500年)に渡来します。日本ではイチハツ(一初 Iris tectorum)と名づけられたこのアヤメは、乾燥地に強く、繁殖力が旺盛で、傾斜地や土手の土留めに使われました。また火除けになるという俗信やかやぶき屋根の強化のために、屋根の棟上に芝棟植物として盛んに植栽されていました。アヤメの中ではシャガに次いで早く咲き、花はアヤメとジャーマンアイリスの中間といった風情です。シャガと共通して外花被片にとさか状の突起と斑点をもち、縁がややちりちりと縮れ、紫色の大きめのシャガ、というふうに見えなくもありません。
そして葉は、基部から中央にかけてはヒオウギやヒオウギアヤメの檜扇の形状に近いながら、先端はやわらかくしなって、シャガの葉にも似ています。
『和漢三才図絵』(寺島良安 1712年)では烏扇(からすおうぎ・ひおうぎ)を別名射干・しやがとしていますが、当時既に「胡蝶花」というシャガの別名に、「こちょうか」ではなく「しやが」のルビを振った文献も見られ、「しゃが」という名が江戸時代前期には既にヒオウギから転意してしまっていることがわかります。
さらに、それより少し前の『花壇地錦抄』(伊藤伊兵衛 1695年)ではイチハツについての説明で、「鳶尾」の文字に「しやが」と訓みをあてていて、一方現代のシャガについては「筋鳶尾」「すじしやが」と言う名称をあてているのです。
つまり「シャガ」という名はどうもまずイチハツに転意され、ついでシャガに移行したようなのです。

手足を広げた人形のようにも見えるため「にんぎょうばな」の方言名も
ヒオウギとイチハツはたいして似ていませんが、ヒオウギアヤメには似ています。ヒオウギ→ヒオウギアヤメ→イチハツ、とグラデーションが形成されます。
また、ヒオウギやヒオウギアヤメはシャガとはまったく似ていませんが、イチハツが間に入るとここもグラデーションが形成されます。人里植物としてより身近な存在のイチハツや胡蝶花が、こうしていつしか「射干=シャガ」を指す言葉へと変化していってしまったのではないでしょうか。
中世に渡来したイチハツやシャガには、定まった和名がないこと、そしてイチハツとシャガに共通するある特徴、つまりイチハツの外花被片の白い毛状のとさか突起、シャガの外花被片の白いレース縁と白い毛状花柱枝が関係していたことが考えられます。
伊豆諸島の八丈島に残る特徴的な方言「八丈方言」は、上代から中世ごろの日常会話語に近い、といわれています。この八丈方言で「しゃが」という言葉は白髪を意味します。中世の庶民は、渡来してきた新しい植物にある特徴的な白い毛状突起を、白髪(しゃが)のようだ、と思ったのではないでしょうか。射干(しゃかん)と「しゃが」の偶然の共鳴。こうして今のシャガが「射干=シャガ」と呼ばれるようになったという推測が成り立ちます。
不思議な歴史の綾を秘めて、今年も人気の少ない暗い林下に、ひっそりとシャガの花が咲き出しています。
(参考・参照)
植物の世界 朝日新聞社
山科家礼記 (第13冊)
花壇地錦抄
和漢三才図絵