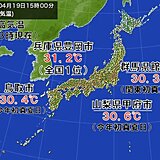その繊細な魔境は唯一無比。3月24日は梶井基次郎の忌日「檸檬忌」

「檸檬」は多くの青年たちに鮮烈な印象を与えました
レモンといえば梶井基次郎、といわれるほど、仲間とともに創刊した同人誌『青空』に発表した小説「檸檬(れもん)」は、国語の教科書にもたびたび取り上げられ、多くの思春期の若者に強い印象を与えた極めて有名な小説です。
これにちなみ、仲春にあたるこの忌日は「檸檬忌」と呼ばれ、大阪の梶井基次郎の墓には、今もファンがレモンを供えて弔っています。
侍の風貌に秘められたふるえる神経。基次郎の生い立ち

伊豆湯ヶ島・湯治時代は文学者たちとの交流と奇行蛮行エピソードだらけ
生来頑健な体質だった基次郎は、肺病を患う祖母の飴を回し舐めしたために肺病に罹患としたといわれ、のちに基次郎の命を奪うことになります。
基次郎の性格をよくあらわすエピソードとして、15歳の中学時代、同居していた異母弟順三が、小学校修了と同時に奉公に出され、異母弟を哀れに思った基次郎は中学を自ら退学し、自身も丁稚奉公に就いたのでした。
基次郎の行動により父親は、奉公に出した順三を家に呼び戻し、基次郎も中学に復学しました。こうした兄弟思いの性質は、習作「夕凪橋の狸」でも、実弟二人が軍艦を見るために無断で遠出をした騒動の顛末で、上の弟には厳しいのに末の弟には甘い両親に対して理不尽さを抱く気持ちにもよくあらわされています。
帰りが遅くなり、叱責を恐れて身を固くしている次弟と比べて、叱責されることは微塵も予期していない末弟が無邪気に父母にすがりついて泣き、兄に責任をなすりつけている様子にもやもやして、末弟を呼びつけて怪談で脅かしてこらしめてやろうと画策するなど、なかなかユーモラスな佳品で、作中でも言及されているように、志賀直哉の家族を題材にした小説の影響が強く見られます。肉親へのアンビバレンツな感情を赤裸々に叙述した「矛盾のような真実」といった作品もあります。
ただ、長男である志賀直哉は、その父が関与した足尾鉱毒事件で父を責め、一時期断絶状態になるほどまでに激しく対立しましたが、中間子でかつ次男の基次郎はリアリスト。作中で父や母への不満や批判は描かれるものの、決定的な対立は避ける世渡り上手な一面もありました。
これが悪く出たのか、基次郎は酒癖の悪かった父親に反発するのではなく、それを踏襲するように酒を飲んでは狼藉を働きました。店の看板を壊す、他人の酒席に裸で乱入する、やくざと乱闘してビール瓶で殴られて気絶する、夫のある女性(宇野千代)に恋慕して、その夫を侮辱して殴り合いをする、海に飛び込んで大怪我をする、などなど、どうしようもないエピソードは数知れず。いかつい侍のような風貌で友人からは「熊」とも呼ばれていたそうです。
後の交友・社会生活における言動振る舞いを見ていくと、もうどうにもならないほど自滅的で滅茶苦茶な生活ぶりで、肺病をこじらせた原因にもなったのでしょう。
遅咲きの天才は桜のように一瞬で花開く

「交尾」はカジカガエルを題材にした珠玉の傑作
桜の樹の下には屍体が埋まっている!
これは信じていいことなんだよ。何故って、桜の花があんなにも見事に咲くなんて信じられないことじゃないか。(「桜の樹の下には」)
その奇妙なたくらみは、むしろ私をぎょっとさせた。(「檸檬」)
「ああかかる日のかかるひととき」
「ああかかる日のかかるひととき」
いつ用意したとも知れないそんな言葉が、ひらひらとひらめいた。(「城のある町にて」)
そればかりではなく、読み手のツボをくすぐる、実に上手い印象的なタイトルをつけることもたくみでした。既に言及した「桜の樹の下には」は、もちろん、「Kの昇天」「闇の絵巻」「器楽的幻覚」「ある崖上の感情」「裸像を盗む男」「夕凪橋の狸」「栗鼠は籠にはいっている」「琴を持った乞食と舞踏人形」「藪熊亭」…何とも奇抜でありミステリアスでもあり、読む前からわくわくさせられてしまいます。
「冬の蠅」「愛撫」「交尾」「卑怯者」、そして「檸檬」などのストレートでシンプルなタイトルもまた、凡庸になってしまうぎりぎりのところで絶妙にコーナーをついてくる名表題です。
この卓抜したセンスを彼がどこから得たのか、いつも不思議になります。もともとエンジニアを目指して理科系高校に進んでいた基次郎は、17歳の頃に結核が悪化して学校を長期休学した際に、兄から借りた夏目漱石や森鴎外の作品を耽読したことから文学に目覚めたといわれ、文学者としての出発は遅かったのです。
散逸して内容は不明の処女作は二十歳頃で、しかしその翌年から二年後には、後の作品と比べれば、若干粗荒ながらも、すでに無駄のない、要を得た確立した文体の作品を完成させるようになっていました。
ともするとベテラン作家のように、読み手の気持ちをぱっとつかむコツを心得たかのような若き日の習作を読むと、間違いなく彼が天才だったと理解できます。
人ならざるものへ…凝視の果てのエロスとタナトス

繊細な感覚が編み出す描写は読む者にときに戦慄を喚起させます
特に初期の習作や未定稿の中には、眩暈のするような観察への没入が描写されています。「闇の書」という、気味の悪い、しかし美しい短編があります。梶井らしき語り手の「私」は、自分の母、しかし自分が見知らない若い娘のような母(のような人)と散歩をしながら、見晴らしのよい高台から景色を眺めています。
「僕はここへ来るといつもあの路を眺めることにしているんです。あすこを人が通ってゆくのを見ているのです。僕はあの路を不思議な路だと思うんです」
「どんな風に不思議なの」(中略)
「譬えば遠くの人を望遠鏡で見るでしょう。すると遠くでわからなかったその人の身体つきや表情が見えて、その人がいまどんなことを考えているかどんな感情に支配されているかというようなことまでが眼鏡のなかへ入って来るでしょう。ちょうどそれと同じなんです。(中略)御覧なさい。人がいなくなるとあの路はどれくらいの大きさに見えて人が通っていたかもわからなくなるでしょう。あんな風にしてあの路は人を待ってるんだ」
私は不思議な情熱が私の胸を圧して来るのを感じながら、凝(じ)っとその路に見入っていた。(中略)
「あの路へ歩いてゆきましょう。あの路へ歩いて出ましょう。私達はどんなに見えるでしょう」
「ええ、歩いてゆきましょう」華やかに母は云った。「でも私達がどんなにちいさく見えるかというのは誰が見るの」(「闇の書」)
見るものと見られるものの奇怪な交錯・倒錯。「見る」行為は、主体から客体へといつしか自身が変容してしまう恍惚を梶井にもたらしたようです。
それが物体に凝固したものが、丸善の洋書売り場に置き去りにされる檸檬であり、檸檬は仮託された梶井なのです。檸檬と化した梶井は、丸裸で他人に「見られる」ことで奇妙な興奮にかられるのです。
「Kの昇天」では、海べりで月光の中に出来た自分の影を凝視することで浮遊感覚を得た男が、やがて波に飲まれて絶命する物語が描かれます。

桜の樹の下には…「檸檬忌」は梶井基次郎を偲ぶのに最適な著作
芥川龍之介は人間が河童の世界へ行く小説を書いたが、河童の世界というものは案外近くにあるものだ。私は一度私の眼の下にいた一匹の河鹿から忽然としてそんな世界に入ってしまった。(中略)私はこの時の来るのを待っていた。すると、案の定、雄はその烈しい鳴き方をひたと鳴きやめたと思う間に、するすると石を下りて水を渡りはじめた。このときその可憐な風情ほど私を感動させたものはなかった。彼が水の上を雌に求め寄ってゆく、それは人間の子供が母親を見つけて甘え泣きに泣きながら駆け寄って行くときと少しも変わったことはない。「ギョ・ギョ・ギョ・ギョ」と鳴きながら泳いで行くのである。こんな一心にも可憐な求愛があるものだろうか。それには私はすっかりあてられてしまったのである。
勿論彼は幸福に雌の足下へ到り着いた。それから彼らは交尾した。爽やかな清流のなかで。(中略)世にも美しいものを見た気持ちで、しばらく私は瀬を揺がす河鹿の声の中に没していた。(「交尾」)
この作品は、梶井がはじめて世に認められた作品で、これにより原稿料を手にし、原稿執筆の依頼も舞い込むことになりました。
しかし、「のんきな患者」を皮切りに、本格的な作家生活に入ろうというそのときには、梶井にはもう人生の時間が残されていませんでした。享年31歳。この後いよいよすごい作品が生み出されたであろうに、と思うと早すぎる死は残念でなりません。
レモンと並び、桜も梶井基次郎のシンボルといえます。桜の花が開花しはじめていますが、今年は花見宴会の自粛が要請されています。桜の樹の下でじっくりと花と向き合い、梶井作品を紐解く、そんな落ち着いた花見をするよい機会なのではないでしょうか。
梶井基次郎全集 筑摩書房
梶井基次郎墓