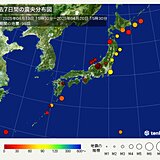クリスマス。イエス生誕の物語は、どうして私たちの心を打つのでしょうか?

クリスマス・クリブ
本場のクリスマスはエピファニーまで12日間も続きます

世界のキリスト教国では24日の日没から翌年1月5日までの12日間がクリスマス期間となります。そして翌日1月6日がEpiphany(エピファニー)。西方教会(カトリック、プロテスタント)では公現祭、東方教会(正教会/オーソドキシー)では神現祭と呼ばれる祝祭日となります。
西方教会ではこの日を東方の三賢者(三博士とも)が星の導きを頼りに幼子イエスを訪ねあて、礼拝した記念日とされていますが、もともとは1月6日とは、ヨルダン川でイエスが洗礼者ヨハネから受洗(浸礼・洗礼)を受け、神の霊が鳩の形をとってイエスの肉体にくだった、つまりイエスという人間の体に、初めて神の本体が宿って、人の目にも顕現した=神現祭で、神であるキリストの実質的な生誕の日、とも考えられている重要な祝祭日となっていました。
なぜ1月6日なのかは、新石器時代に起源を持つ、聖処女神コレー(Κόρη/Kovrh/Ker/Car/Q're/Core)の祝祭日「コレーイオン」と関係があるといわれています。この日、コレーが時間の神とされるアイオーン(AEON)を処女のまま産み落とした、とする神話があったのです。キリスト教がローマ帝国やその周辺で信仰信者を獲得していく過程で、コレー信仰を習合する形で神現祭へと成り代わっていきますが、更に冬至にあたる12月25日前後をミトラ神の生誕日として祝っていたミトラ教も吸収する過程で、イエスの生誕は12月25日へと定着していきました。
ちなみにローマカトリックでは三位一体の神は完全無欠であり、イエス・キリストも元から完璧な存在なので、洗礼という通過儀礼を受けること自体が矛盾するという考えのもと、この受洗の意味を「人々に洗礼を勧める神の模範」とするなど、小さな出来事として解釈したため、本来の「キリスト受洗の神現祭」から、「三賢者が訪れ、異教の者たちにもキリストの光がもたらされた記念すべき日」公現祭へと意味合いが変わったのでした。
意味深な「三人のマギ」によってあらわされたものとは

イエスは、ヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。そのとき、占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来て、言った。「ユダヤ人の王としてお生まれになった方は、どこにおられますか。わたしたちは東方でその星を見たので、拝みに来たのです。」(中略)出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると、幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて、黄金、乳香、没薬(もつやく)を贈り物として捧げた。(「マタイによる福音書」2章)
彼ら(※註 ヨセフとマリア)がベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて、初めての子を産み、布にくるんで飼い葉桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら、夜通し羊の群れの番をしていた。すると、主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので、彼らは非常に恐れた。(中略)天使たちが離れて天に去ったとき、羊飼いたちは、「さあ、ベツレヘムに行こう。主が知らせてくださったその出来事を見ようではないか。」と話し合った。そして急いで行って、マリアとヨセフ、また飼い葉桶に寝かせてある乳飲み子を探し当てた。(「ルカによる福音書」2章)
生まれたばかりのイエスを訪うのは、マタイ伝では「占星術の学者たち」で、ルカ伝では「羊飼いたち」です。羊飼いはともかく、謎めいた「占星術の学者たち」とは、「ギリシャ語聖書」の原文ではμάγοι(マゴイ)で、また原文にも訳文にも学者たちの人数は記述されていません。しかし、イエスに捧げたのが三つの贈り物だったことからか、神学者オリゲネスの説により三世紀ごろに学者たちの数は三人とする説が出てきて、次第に定型が出来上がり、「東方の三博士」「東方の三王」などという呼び名も使われるようになっていきます。μάγοι(マゴイ)とはラテン語ではマギ(magi)で、英語のmagician(魔術師)の語源にもなっています。ペルシャ・アナトリアの占星術師とも推測され、古代ローマの壁画では、フリュギア帽(先端が前に折れたとんがり帽)をかぶったミトラ教の祭司の衣装をまとって彫られています。7~8世紀のアングロ・サクソンの神学者ベーダ(Baeda)は、この三人を白髪の老人メルキオール、ひげのない若者のカスパール、浅黒い肌をした壮年のパルタザール、とそれぞれに名前と風貌を与えて著作に記載し、以来これに基づいて賢者たちは描かれるようになりました。特に「褐色の肌のパルタザール」は、後に次第に黒人として解釈されるようになり、三賢者は、さまざまな人種・民族を統治統合する世界宗教としてのキリスト教の理念をあらわす図像となっていきました。
ベツレヘムの馬小屋に生まれ落ちたのはイエス?それとも…

それにしてもどうしてイエスの生誕譚は、キリスト教信者でもない世界中の人々の心を捉えるのでしょうか。
ヨセフとマリアは身分も高くなく金もない、どこにでもいる若いカップルです。旅先で泊めてくれる宿はなく、仕方なく家畜小屋(または洞窟)で暖を取り、肩を寄せ合うようにして子どもを産み落とします。境遇としては恵まれているとは到底言いがたい二人に、大多数の厳しい生活を送る庶民が共感を寄せるのは自然なことだったはずです。
すると、このよりどころもないわびしげな一家に、星が光って天の祝福が。身分の低い羊飼いや、高貴な賢者(王)たち、そして牛や羊などの動物たちもその誕生を喜び、祝福します。イエス生誕の物語は一人特別なキリストの生誕ではなく、この世に生を受けた全ての人、私たち一人ひとりが、その生誕を、両親、そして世界から祝福されて生まれてきたのだ、と追体験する物語ともなったのです。ベツレヘムの馬小屋で生まれたのは、イエスでもあり、また自分自身でもある、と重ねることが出来るからこそ、この神話は普遍性をもって人に温かさと感動を与えるのではないでしょうか。
聖書(新共同訳) 日本聖書協会
世界の宗教と経典 自由国民社