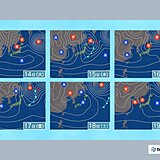二十四節気「秋分」。秋の野辺・水辺はタデ科の花盛り

タデ科は、北半球を中心に45属1,000種以上の種が知られる大きな植物群です。日本には60種ほどが自生します。極めて人間と関わりが深い個性的な代表種を紹介しましょう。
のどかな田園のシンボル・アカマンマ、スカンポ…そして大人の味わいヤナギタデ

イヌタデ
秋のイヌタデ=アカマンマに対して、春の野辺で子供たちのままごとのお供となるのがスイバ(Rumex acetosa)。スイバは「酸い葉」で、葉にシュウ酸由来の酸味があるため、たわむれに噛んで遊んだり、泡立つような房になるエンジ色の花穂をしごいて、やはり赤飯のようにしたり、葉を菜っ葉のようにして遊びました。スカンポ、という名の方が通りがいいかもしれません。ままごと遊びだけではなく、スイバも、また同じ時期に地面からアスパラガスのように伸び出てくるイタドリも、春の美味しい山菜として実際に食べられます。フランス料理ではスイバはoseille(オゼイユ)またはsorrel(ソレル)という名で、肉料理の付け合せや、ペースト状にしたソース、緑の鮮やかなスープなどに使われます。
「イヌタデ」に対して「ホンタデ」とも言われるのが葉や茎に辛味があるため刺身のツマなどにして食べられるヤナギタデ(Persicaria hydropiper)です。イヌタデよりもやや草丈は高く、60センチほど。細いヤナギのような葉をつけるため柳蓼といわれます。花は薄いピンクで、花穂の花つきはまばらですがその分涼しげでしゅっとした印象を与えます。このヤナギタデを栽培したものが、シソの花穂とともに刺身のつまとなるムラサキタデやアオタデです。食べるとぴりりとする強い辛味成分タデオナール(Tadeonal)は、魚の生臭みを消し、殺菌作用があるため食中毒を防ぐといわれています。また、ヤナギタデの若芽(通常アオタデと呼ばれるもの)を少量の塩とともにすりつぶして飯粒で伸ばし、酢を適宜あわせたものが「蓼酢」で、鮎の塩焼きのほか、イサキやスズキなどの磯魚にもよくあいます。
美しさとおぞましさ。どっちもタデ科のかわいい花なのに

ミズヒキの花
水引草に風が立ち
草ひばりのうたひやまない
しづまりかへつた午さがりの林道を
(立原道造「のちのおもひに」より)
この心震える美しいフレーズで読まれている「水引草」=ミズヒキ(Persicaria filiformis)も、タデ科の一種です。森林や公園の木立の下など、日陰になった場所ならばどこにでも生える、ごく普通に見られる野草です。細長い糸のような柄にまばらに粒のような花をつけます。四弁で、上部三枚が鮮やかな赤、下一枚が白の紅白で、このため結婚式などの慶事の水引になぞらえられて、その名がつきました。
そんな綺麗な名を与えられた種があるかと思えば、おそらく日本の植物では最悪であろう名前をつけられた種もあります。ママコノシリヌグイ(継子の尻拭い Persicaria senticosa)です。水辺に生えるタデ科の草本で、紙が貴重だった時代、便所の落とし紙には通常植物の葉を用いました。アジサイの葉などはその典型ですが、そんな葉ですら継子、つまり再婚相手の連れ子に使うのは惜しい、とこの草をお尻拭きに使わせる、というのです。ママコノシリヌグイには茎に他の植物に絡みつくために下向きに鋭い棘が生えていて、下手につかむと痛い思いをします。そんな植物でお尻を拭いたら……想像もしたくないですが、植物学者牧野富太郎はこの名を正式種名としました。ママコノシリヌグイやアキノウナギツカミ、ミゾソバなどの水辺近くに生えるタデ科の仲間は、葉が三角形をしていることと、花が穂にならず、小さな丸い塊になるものが多く、その形がお菓子の金平糖に似ているため、「こんぺとぐさ」「こんぺとばな」などというかわいらしい名前もついています。
和食に染物に……日本人とは切っても切れない深い仲のタデ

藍の花
ソバと並んで人間にとって長く大切にされてきたタデ科の植物にタデアイ(蓼藍 Persicaria tinctoria)があります。草丈は50〜70センチほど、見た目はイヌタデやヤナギタデによく似ています。けれども葉を傷つけると、細胞から濃い青の色素(インディゴ)が滲み出します。人工合成染料が開発される以前は、このタデアイで藍染めをしていました。防虫性や防火性に優れ、藍染めの布地は長く野良着、作業着として重宝されてきました。
「蓼」って何のこと?漢字の成り立ちからわかる本当の意味

金文(鍾鼎文=しょうていぶん。殷・周時代の青銅器に刻まれた古代文字)では、翏の文字は上部分が鹿の角、下部分は鹿が吐く息をあらわし、全体で「繁殖期の雄鹿が鳴く様子」を表しているのです。そしてそれに草かんむりを配した「蓼」とは、草むらに雄鹿が群れている様を現します。オンタデやオオイヌタデなどが、分岐した枝葉が突き出すような花穂をつけ、風に揺れている様子を、草むらにいる鹿の角に見立てるのはよくわかるし腑に落ちます。「蓼」の名は、その意味でつけられたと考えるのが自然ではないでしょうか。日本では鹿は秋の季語。タデの由来にもぴったりです。
では一方、日本語の「たで」は何に由来するのでしょうか。新撰字鏡(898年~901年)ではタデを「太氐(たてい)」と表記し、平安時代ごろの貴族階級は「たてい」「たて」と読んでいたようです。現在でも離島などではタデを「タディ」「サデ」などの方言が残っており、「たてい」は上流階級によるその清音化でしょう。身近な野の草であるタデは、古くから民間生薬として利用されてきました。虫に刺されたときにはその葉を揉んで患部に汁をつけるほか、扁桃炎や口内炎、歯槽膿漏などでは、茎葉を煎じたものをうがい薬に、しもやけには刻んだ茎葉をお湯に浸し、その中でよく揉むと効果がある、とされました。つまり「ただれ=炎症」に効果のある身近な薬だったため、「ただれの薬になる草」から「たで」と呼ばれるようになったのだと考えられます。
野草の料理 (甘糟幸子 中公文庫)
薬草カラー図鑑 (講談社)
植物の世界 (朝日新聞社)
立原道造詩集 (岩波文庫)