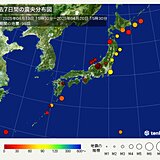「もののあはれ」川端康成が憧れた究極の聖性とは?4月16日「康成忌」

晴れのひのき舞台で垣間見えた川端康成の虚無

しかし、教科書で見た写真の中の川端康成は、少年時代の筆者には憮然としていてあまり受賞を喜んでいるようには見えず、体の大きなヨーロッパ人に囲まれている紋付はかま姿のひときわ小柄な老人が、異界から人間界に迷い込み、孤独と敵意を内に秘めた人ならざる魔物のように見えたのでした。後に川端作品や評伝を読み、川端が若い頃から「ノーベル賞だけは獲りたいと思っている」と執念を見せ、また自身が文壇デビューをさせ、川端と同時期にノーベル賞候補でもあった三島由紀夫に、ノーベルアカデミーに推薦文を書いてもらうなどの政治活動をし、受賞後のインタビューではうれしさをにじませていたことなどを知り、写真から受けた印象は正しくはないことを知りました。
川端がなぜそこまでノーベル賞にこだわったのかはわかりません。しかし、受賞のわずか4年後に自殺(事故死であるとの異論もありますが)の道を選んでしまったことを鑑みると、あの授賞式で川端が全身から漂わせているように筆者には見えた孤愁や虚無の気配は、あながち間違いではなかったのではないか、とも思えるのです。川端は、「美しい日本に生まれた私」という著作で、日本の古い伝統文化への誇りと偏愛を明確に打ち出してます。にもかかわらず、ノーベル賞を本当に心底欲したのでしょうか。この極度のアンビバレンツは何なのでしょうか。
「魔界」の目が彫塑する魔性の川端文学

川端康成生誕の碑
川端作品に特徴的な偏執的な官能(五感)へのこだわり、人肌、そして人体パーツへの固執と見つめる陶酔、死の予感と恐怖、その果てに立ち現れる心霊的・神秘的雰囲気は、数奇な生い立ちからくるものかもしれません。
川端康成と言うと、誰もが知る「雪国」や「伊豆の踊り子」のイメージが強いですが、犬や小鳥などのペットを愛し、その生き死にを執拗に観察する変人の男を描いた「禽獣」、心霊的な幻想の中の絆を描く「叙情歌」、裸の娘を昏睡させて添い寝するだけの変態的娼館を訪れた老人の性欲を描いた「眠れる美女」、醜い容姿をもつ主人公銀平が、美しい少女を執拗に付けまわし、妄想にふける前編が背徳にいろどられた「みづうみ」など、川端文学の底流には、強烈なフェティシズムとインモラルが横たわっていて、読む者をいやおうなく引き込みます。
川端自身は普段は温厚で義侠心にあふれる人格者でしたが、若き日の13歳の少女・伊藤初代との恋愛や婚約、寄宿学校時代の同室の下級生の少年・小笠原義人との熱烈な恋情など、美しいもの、官能的なものを眼前にしたときに人間社会のモラルや常識をたやすく逸脱する側面もありました。もちろん表現者たるもの、誰しも己の中に人間社会とは相容れない小さな魔物を飼ってはいるでしょう。しかし川端の場合、取りついていたのは並みの魔物ではなく、高い位階とパワーをもつ「魔王」でした。
一例として、川端が見出し、愛でた古美術品の中に、後に国宝となったものが3点も存在しています。「小説の神様」志賀直哉にも骨董への深い造詣がありましたが、志賀の所蔵から後に国宝が出たということはありません。志賀の趣味の傾向が民芸品で川端は古美術であるという違いはあるでしょうが、美の魔王に取りつかれた川端の審美眼が、尋常ならざるものだったことが見て取れます。
代表作「山の音」の一節。老境の信吾が密かに恋情を抱いている息子の嫁である菊子。息子夫婦に別れ話が持ち上がっていたあるとき、信吾は所蔵の骨董の能面を菊子に見せます。すると菊子が戯れにその面をかぶります。
艶めかしい少年の面をつけた顔を、菊子がいろいろに動かすのを、信吾は見ていられなかった。
菊子は顔が小さいので、あごのさきもほとんど面にかくれていたが、その見えるか見えないかのあごから喉へ、涙が流れて伝わった。涙は二筋になり、三筋になり、流れつづけた。(「山の音」~春の鐘)
夫の不義に気丈に振舞っていた若い嫁が、能面の奥で図らずも嗚咽号泣する、いかにも日本的な哀しみの感情表現。菊子のいじらしさとともどもに、それを見る義父である信吾は口には出せない暗い情念に悶えているのです。まさに魔王こそが描ける、深閑とした美しい背徳の情景です。
「古の山河にひとり還ってゆくばかり」ノーベル賞への執念との矛盾

川端は、自分の受賞はサイデンステッカーの絶妙な翻訳のおかげだ、と語っていますが、翻訳により、どこまで川端作品の本質が欧米人に伝わっていたのかは正直わかりませんが、川端作品の深遠さと比べて、川端が口や評論で語る「日本の美」「日本の伝統」はどこか表層的でおざなりなものに感じられます。まるで、小説家としての美の求道的魔人である川端と、それを売り込むマネージャーである俗人川端が一人の人間のなかに同居していて、喋りや評論時には俗人川端が表に出ているかのような乖離と落差を感じてしまうのは、筆者だけでしょうか。
「私の生涯は「出発まで」もなく、さうしてすでに終つたと、今は感ぜられてならない。古の山河にひとり還つてゆくだけである。」(「島木健作追悼」)
このように述懐した川端と、貪欲にノーベル賞を欲した川端とは同じ人格とは思えないのです。
川端康成・死の深層と「フルーツバスケット」

川端の死の直接の原因として噂話的に語られるのは、自殺の直前、川端家に奉公していた女中兼運転手を勤めていた鹿沢縫子(仮名)が奉公をやめたことが引き金となったという説です。やめたいという縫子を養女にしたいとまで考えていた川端は、引き止めますが、それが叶わず「そうですか、だめですか」と深く落胆したと伝わっています。「フルーツバスケット」の透が、旧家の呪いにかかった人たちを次々と救っていくのに対して、縫子は川端家から立ち去ってしまいます。もし縫子が透のようであったならば、また違った結末が待っていたのかもしれません。
魔人川端は、最後の供物として川端康成本人の命を欲しました。栄光が大きかった分、川端の絶望は暗く深いものとして彼を飲み込んでしまったように思えてなりません。
筆者がもっとも好きな川端作品は「川のある下町の話」です。中にこんな台詞があります。
「つばめをごらんなさい。日本が戦争に敗けても、占領されても、つばめはなつかしい日本へ、南の国から子を生みに来た。外国から来る奴で、態度の変わらないのは、つばめだけじゃありませんか。」(「川のある下町の話」)
川端は、仏教の輪廻転生の教義や仏典も、「人間の作った美しい抒情詩」と語っていました。しかし、その「抒情詩」=仏法も結局は「人間」を上位とし、他の命たちを下に置いていて、日本古来の悲しみ=「もののあはれ」とはちがう。「もののあはれ」とは人間至上主義ではなく、生きるもの死んだものすべての悲しみを等しく共有する心であると。
川端康成が旅立ち、帰って行ったのは、どこだったのでしょうか。
参照
山の音 (川端康成 新潮文庫)
川のある下町の話 (川端康成 新潮文庫)
フルーツバスケット (高屋奈月 白泉社)
LLL 「川端康成とノーベル文学賞 ・スウェーデンアカデミー所蔵の選考資料をめぐって」大木ひさよ::https://archives.bukkyo-u.ac.jp/rp-contents/KG/0021/KG00210L042.pdfLLL