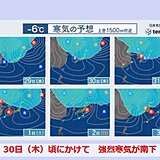季節を代表する花、梅の「におい」── 言葉の移り変わりを味わう

梅とメジロ
今日は祝日(建国記念日)、そして明日は日曜日……。連休に梅の鑑賞に出かけられる方も多いのではないでしょうか。
春の訪れをいち早く私たちに感じさせてくれる梅ですが、その香りは梅、花の姿は桜、などとも言われます。
ところが、古代から中世では、「におい」は必ずしも嗅覚にまつわる言葉ではなかったのです。
「におい」は視覚的な言葉だった
もともと中国から渡来した植物で、梅をめでることそのものが文化として日本に根づいたのは、中国文化の影響によるものとされています。
梅はその香りが好まれてきましたが、嗅覚についての感覚を表す言葉「におい」は、もともとは視覚的な感覚をあらわす言葉だったのです。
日本古代の詩歌を読んでみると、たとえば……、
〈梅の花にほひの深く見えつるは春の隣の近きなりけり〉三統元夏(みむねのもとなつ)
梅の花の色が深く見えているのはもうすぐ春のやってくる知らせだ、というのですが、この歌で「にほひ」が「見え」という言葉とともに使われていることでわかるように、「にほひ」はもともと花の色などが人の感覚を刺激することを形容する言葉でした。
さまざまな意味を持つ「におい」
「源氏物語」では光源氏の幼いころの美しさを形容する部分では
……御にほひには並び給ふべくもあらざりければ……(「桐壷」)
などと使われました。
さらに意味が転じて「にほひ」は、立派さ、気品のあるようす、栄光などを形容する言葉、たとえば宮廷の官僚としての目覚ましい出世をたたえる言葉としても使われるようになります。
視覚から嗅覚へ

雪の残る大阪城公園の梅林
しかしそのような意味でも使われ始めたのは、奈良時代の末期頃からであると、国文学研究では考えられています。人の感覚を強く刺激する花の美しさなどが、多く香りも伴うものであったところから、「におい」が、嗅覚についての意味を含むようになっていきました。
したがって平安時代の和歌では「におい」は、視覚と嗅覚とを同時に刺激するような、色艶・香りがともに優れているような美しさを意味するようになりました。
のちには「におい」という言葉は、嗅覚的な徐々に及んでくるような感覚・雰囲気や気分を表す言葉として、また配色の美しさをいう言葉ともなりました。
言葉は長い時間をかけて意味が変わっていきます。変わった後にももとの意味がかすかに残ることもあります。
「におい」にも、歴史の時間が積もった複雑なニュアンスが感じられます。季節の言葉に歴史を感じてみると、いっそう味わい深くなるのではないでしょうか。