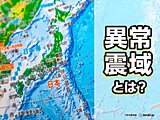秋の夜に降り注ぐゴールデンベル。謎多き葉陰の忍者・アオマツムシとは?

この時期、鈴のような音色を降らせるアオマツムシ
コオロギ界の小さな異端児は、なぜ大きな音を出せる?

樹木の葉にまぎれるアオマツムシの雌。木の葉隠れの忍びのようです
青いポプラの並木道を 鞭をふりふり駆けてゆく(『夢のお馬車』)
秋、街路樹や公園の植栽からそのシャンシャンリンリンとさざめく鳴き声を聞くたびに、筆者はこの童謡を思い浮かべてしまいます。その華やかな声の主はアオマツムシ(青松虫 Truljalia hibinonis) 。バッタ目コオロギ亜目マツムシ科アオマツムシ属に属する昆虫で、本州以南の全国に分布し、夏から秋にかけて鳴くコオロギの仲間です。
体長は、雄が20~22mm、雌が22~25mmほどですが、翅は胴よりも5mmほど長く、実際より大きく見えます。雌は全身が脚も含めて鮮やかな若葉色の緑、雄は上翅(鳴き声を奏でる部分)に複雑な褐色の網目模様が入るほかは雌と同様の若葉色で、雌雄とも体の両脇にレモン色のラインが入ります。
コオロギの仲間はほとんど地上性ですが、アオマツムシは珍しい樹上性で、ケヤキやエノキ、サクラ、トウカエデ、スズカケ、ユリノキなどの落葉/常緑中高木の樹冠に好んで生息します。アオマツムシ属(Truljalia)は、英語圏ではtree cricket=樹のコオロギと呼びます。全身のかたちは背側が極端に扁平で上から見ると披針形で、緑色の体色とあいまってまさに葉っぱそのもの。どれほど声のするあたりに目を凝らしても、葉に紛れてしまい見つけることはなかなかできません。後肢はほっそりとしていて、地上性のコオロギのように発達した後肢でジャンプはできず、そのかわり飛翔することは得意です。
コオロギの仲間とはかけはなれた外見をした、個性豊かな昆虫です。
鳴き声は、リルルルルル、またはリリュリュリュリュリュ、と聞きなせるもので、歯切れがよく高音で、日本の在来種の中ではスズムシの音色に似ています。ただしスズムシの肌理が細かく高い音と比べるとわずかに低く聞こえ、音色のビブラート(震え)も大きめになります。ちょうどエンマコオロギの、フリュフリュフリュフリュ……と聞こえる震えが大きく温かい低めの音色と、スズムシの音色の中間といえばいいでしょうか。スズムシがビオラでエンマコオロギがチェロなら、アオマツムシはバイオリンというところでしょう。鳴く虫のたてる音量は体格に普通比例します。大きな体躯のクツワムシやキリギリス、エンマコオロギはやはり大きな音を出します。ところが遥かに小さく華奢なアオマツムシの雄は、その体格と比べると極めて大きな音を出します。
その秘密は、その翅の構造と形状にあります。飛翔能力を退化させ、翅が短いコオロギ類は、短い翅を45°ほど(スズムシの場合はほぼ90°)に斜めに上げて鳴きます。その翅は、両端が胴体を守るために箱型に折れ曲がっていて、これが翅を上げて音を奏でると、弦楽器の共鳴胴、ピアノの響板のような役割となって音が響くわけですが、アオマツムシは、コオロギ類でありながら長い翅をもつ特異な種です。そしてコオロギ類と同じようにボックス型に折れ曲がっています。この長くかつ箱型の翅を45°~60°に上げて音を鳴らすのです。翅と胴体の共鳴ボックスができあがり体格には不釣り合いな大きな音を奏でることができるのです。
君の故郷はどこ?アオマツムシ発見のストーリーと謎の原産地

東京赤坂の都心部で、世界で初めてアオマツムシが認知されました
明治三十一(1898)年の9月。植物学者の日比野信一(1888~1968年)氏が少年時代、従兄弟と連れ立って銀座から麻布の自宅に帰宅途中。赤坂の榎坂(榎坂の地名は千駄ヶ谷の方にもあり、この二つの榎坂の面白い所以についてはいずれ稿を改めて叙述するつもりです)にあるエノキの大木のそばを通りかかった際、聞いたことのない虫の鳴き声に気づきました。図鑑、虫譜等を探しても見当たりません。18年後の大正五(1916)年、日比野は昆虫学の権威である松村松年(1872~1960年)氏に生体標本を送り、松村博士はこれを新種と断定、翌年正式に学名を申請登録しました。種名のhibinonisは、日比野に献名されたものです。
そしてこの虫が当時赤坂付近にしか確認できなかったこと、中世近世の類書・虫譜に記載がないことから、松村松年以下昆虫学者の面々は外来種であろうと推断し、ではどこから渡って来たのかと議論になりました。松村はインドネシアからと主張し、他の学者はそれぞれマレーシア、フィリピン、中国、インドと推測をぶつけあいました。
この議論は根拠となる素材が乏しく、とりあえず「中国南部」で落ち着きましたが、現代になっても結論は出ておらず、どこから渡って来たのかについては未だ不明のままです。
原産地とされた中国ではどうでしょうか。中国ではアオマツムシを「梨片蟋」=梨の切片のコオロギ、と呼びます。梨の木などの果樹にいることが多いこと、そしてその形が未熟な青い梨の実のかけらのように見えることから名付けられたようです。なかなか風情があり特徴をとらえた名だと思います。
他に「銀琵琶」「緑蛣蛉」「天蛉」(ただし天蛉は邯鄲=カンタンのことも指すようです)と、世にも美しい名をいくつも与えられています。それもそのはずで、中国ではアオマツムシを捕らえて飼育し、鳴き声を楽しむ風習があり、現在でも他の鳴く虫たちとともに飼育され、売買もされています。昭和5(1930)年ごろ、中国杭州に滞在していた昆虫学者の日浦勇氏は、道端で鳴く虫を売る子供を見かけ、「どんな虫が売られているのか」と興味を持って覗いてみると、雌雄のアオマツムシで大変驚いた、というエピソードがあります。子供はアオマツムシを「金鐘児」という名で呼んでいたそうです。金鐘児といえば日本では日本固有種のスズムシの別名として有名です。これはどういうことでしょうか。日本の金鐘児という呼び名が中国に伝わり、鈴の音のような音を奏でるアオマツムシにその名を充てた(つまりその時代にはアオマツムシの独自の名称がなかった?)のでしょうか。ちなみに中国ではスズムシのことを「黒鐘」と呼ぶようです。
近現代に中国でアオマツムシが野生分布し、飼育されていたことも間違いがないのですが、その割には漢籍の古文献を探しても、アオマツムシに言及する資料は見当たりません。あるいは中国においても、東南アジアもしくはインドから、国際貿易が盛んになる近世から近代頃に移入した種なのかもしれません。
明治末期から大正初期にかけて東京の赤坂に出現した集団についても、東・南アジアに分布するアオマツムシの遺伝子系統を調べれば判明するはずで、将来的に調査解明が期待されます。
アオマツムシの汚名に異論あり!在来コオロギ減少の本当の理由は

長い翅は、まさに葉っぱそのものです
たとえば、アオマツムシの鳴き声が大きく情緒がなくうるさい。そうでしょうか。クツワムシのガシャガシャかきならす鳴き声にすら趣きをおぼえるのが日本人のはずなのに……。
また、その鳴き声が倍音構造になっているために、他の在来種の鳴き声をかき消してしまい、繁殖の阻害要因となっている、とすら。たしかにアオマツムシが街路樹に集い一斉に鳴きだしますと、寺院での大人数の僧侶による梵唄(ぼんばい)かのように途切れなくリューリューリューと鳴り渡るように聞こえます。枝という枝に風鈴を括りつけて一斉に鳴らしているような大音量です。「こんなにうるさくては他の虫たちは仲間の鳴き声が聞こえないんじゃないか」と思われるかもしれません。
しかし立ち止まり、じっくり聞き比べて見ると、アオマツムシの大合唱の中でも、コオロギの声はもちろん、控えめなツユムシの声も、小さなクサヒバリの声もちゃんと聞こえてきます。
もしある虫の声が他の虫の邪魔になるというのなら、たとえば音の大きなエンマコオロギの鳴き声が、樹上にいるアオマツムシとは違い生息域もかぶる近縁種のツヅレサセコオロギやオカメコオロギの繁殖の邪魔になってしまうはずですが、そういうことはありません。近年の鳴く虫たちの減少は、人間による草むら、草原の開発による生息地域の減少が原因です。
鳴くことに特化し、飛翔能力を退化・消失させた地上性のコオロギ類、また飛ぶことはできても体が大きく、規模の大きな草原を必要とするキリギリス類は、特に数を大きく減らしています。
それに対して、生息域が中高木の樹冠という特殊なニッチのアオマツムシは、都市部や幹線道路沿いなどに植栽される街路樹を棲み処とし、また飛べるために次々と隣の街路樹へと飛び移り、人間による都市化に適応して、必死に分布域を広げてきただけなのです。決してアオマツムシが在来種を駆逐したわけではありません。
アオマツムシへの悪意は、「この虫をアオゴキブリという」という流言にもあらわれています。筆者が知る限り、アオマツムシを「アオゴキブリ」と呼んでいる人や地域を聞いたことも出会ったこともありません。「そう呼んでいる」という事例があるのなら教えてほしいほどです。全身がエメラルドグリーンのアオマツムシは美しいとしか思えませんがいかがでしょうか。

どこから来たのか不明ながら日本の環境に溶け込み美しい音色を聞かせてくれます
どこから来たのか不明ながら、日本の環境に溶け込み、美しい音色を聞かせてくれます。
参考
森林総合研究所 多摩森林科学園/アオマツムシ(9月)
アオマツムシの素敵な鳴き声
野外観察図鑑 昆虫 旺文社